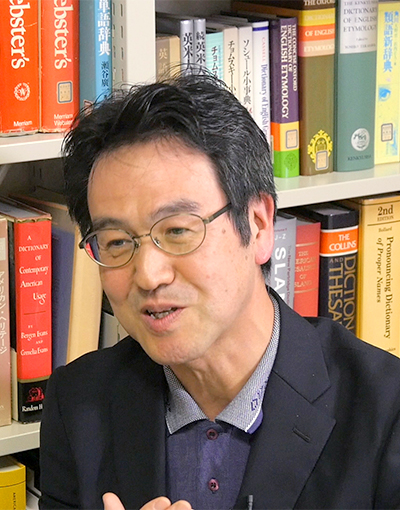この授業では、学生たちが、社会のさまざまな課題から関心のあるテーマを選び、その問題を解決するためのアイデアを探し、グループで発表します。黒板に書かれた内容を理解せずにただノートに取るような受け身の授業ではなく、自分たちで考えたアイデアを形にしていくことがねらいです。自分が主人公になること、今まで経営学部で学んで来たことをフルに生かすこと、そして自分たちが考えたアイデアが人の共感を得られるようグループで知恵を絞って成果物を作っていくという、3つのチャレンジがある授業です。1つのグループは「日本のソーシャルビジネスと労働問題の現状」を取り上げ、労働者の間で格差が広がり、一人一人が分断されているという現状から、労働者同士の横のつながりを大切にするため、定例の労働組合登録会の開催を提案しました。別のグループは、日本における子どもの貧困について調べ、「基本的な教育やきちんとした職業訓練を受けて、将来自立できる仕組みを整えることが国として重要」であると発表しました。発表した学生たちからは「自分の考えを大勢の前で発表したことが貴重な体験になった」「考えるだけでなく、実際に行動に移すことが大切」「この授業が考えるきっかけを与えてくれて、世の中に対する問題意識が強くなった」といった声があがりました。
みなさんにはアイデアを出していくこと、それを世の中に伝えていくことを忘れないでほしいと思います。アイデアは心の中にしまっておかず、どんどん外に出していくことを心掛けてください。
関連コラム:ソーシャルビジネス実習講義 プロジェクト報告会
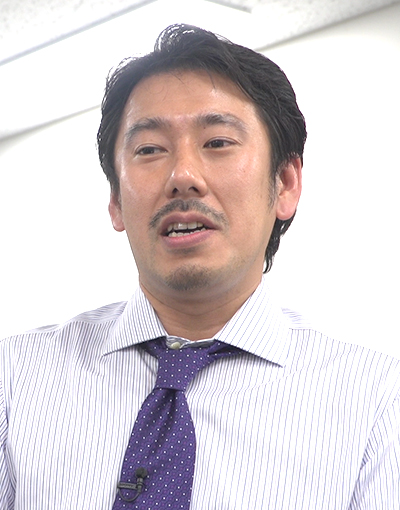
川﨑 健太郎教授経営学部 会計ファイナンス学科
- 専門:国際金融、国際通貨、国際マクロ経済学