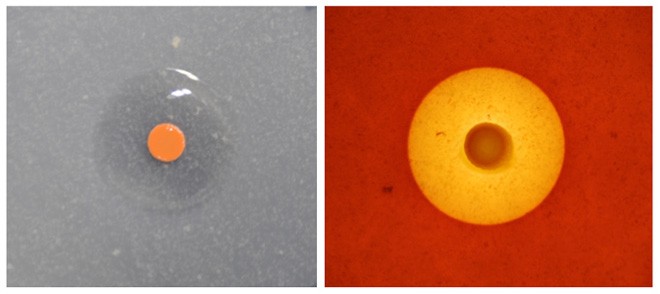極限環境とは、生物の生存を許さないような特殊な環境です。実はこの極限環境は地球の大部分を占めており、そこから微生物が多数発見されています。これら極限環境微生物の分離技術、生理生化学的解析、分類学・生態学的解析、工業的応用などの全てが資源の少ない日本にとって重要な学問分野です。その中でも「高度好塩菌」に着目して研究を進めています。高度好塩菌は好塩性以外にも、好酸性、好アルカリ性、紫外線耐性、耐/好圧性など様々な極限環境因子に適応しており、「polyextremophiles」として注目されています。
好塩菌の1種であるHalosimplex carlsbadenseは太古の岩塩層から分離された現世する最古の生物として知られています。さらに好塩菌は、その性状から火星や木星の衛星であるエウロパ、土星の衛星であるエンケラダスなどの地球外環境でも生息できる可能性が考えられています。近年では深海の熱水鉱床や、低塩濃度環境からも検出・分離報告され、生物の環境適応機構を解明するターゲットとして非情に魅力ある生物です。また、人や動植物とも密接に関わっており、フラミンゴの着色現象の要因、オオミズナギドリの鼻腔からの分離報告などがあります。近年では、脳脊髄炎患者の脳内から好塩菌に特異的な遺伝子が検出されています。
好塩菌を分離し、性状解析や多様性解析などを行い、分布とその生態を解明することは、生物の遺伝的多様性と共通性の謎を解明する手がかりとなり、生命進化・生命起源解明への足がかりにもなると考えられます。一方で、好塩菌が生産する酵素も産業応用への期待が高まっています。好塩性酵素の多くは耐熱性、有機溶媒耐性などの性質を持つ物が多く、様々な条件下で利用が期待されています。解析例も少ないため新規配列や新規化学反応の発見が期待されます。
このように好塩菌研究は、一つの生物種の研究だけでなく、様々な分野への応用展開が可能です。