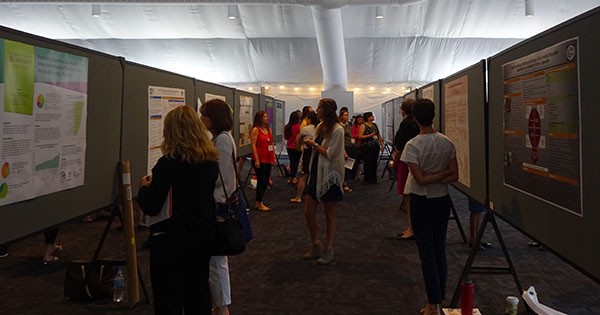当研究室では、人々が持つ食意識と食行動・食事内容の関連性の検討を行っています。これまでは、主に幼児を専門として、好き嫌いの有無とその幼児が持つ食意識の関連性の検討等の研究を実施してきました。その結果、幼児期において、食意識を高める重要性が示唆されました。また、弁当や箸という日本の食文化を意識した、実生活の身近な指標を用いて、保護者の食意識が幼児の食習慣に与える影響を明らかにしてきました。
さらに、人が持つ意識と健康というキーワードから、主観的健康観という指標を活用した研究も進めています。主観的健康観とは、疾病の有無に関わらず健康だと思う意識の指標で、高齢者において主観的健康観の高低と死亡率の関連性が報告されています。高校生を対象とした我々の調査結果では、主観的健康観と食習慣が関連している可能性を示唆しています。このような、国際的に使われている指標を用いることで、各国の現状を確認することができます。
このように、当研究室では、疫学の手法を用いて、普段の生活の中で何気なく行っている食事や生活とその決定に関わる先行因子だと考えられる食意識やもっと広い視野で捉えた健康意識の関連性について、客観的に評価しています。食生活という非常に要因が多く複雑な分野ですが、一つずつ関連性を確認し、研究結果を蓄積し、最終的には食生活に関する意思決定の要因解明に寄与できたらと考えています。
現在進めている主な研究テーマは、1.各ライフステージにおける食嗜好と食意識・食行動・食事内容の関連性の検討、2.食事中の環境や食物が味覚や摂食率に与える影響です。