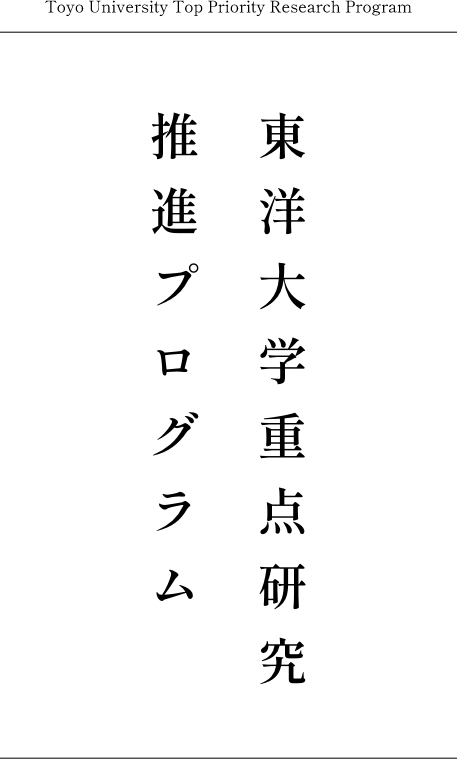

「東洋大学重点研究推進プログラム」は、超スマート社会の到来に向けて、本学における先端的な研究を促進し、世界水準の大学へと発展させることを目標として、2018年に創設されました。
このプログラムは、個々の研究者や1つの研究科で取り組む研究とは異なり、研究領域を超えた文理融合型で学際的なプロジェクトチームとして取り組む研究で、本学における研究のブランド力向上となり得る先端的かつ独創的な研究プロジェクトを重点的に助成しています。採択プロジェクトは、他の研究プロジェクトや井上円了哲学センター等とのコラボレーションに積極的に参画することで、研究の高度化を目指しています。
現在、以下の8つの重点研究課題に基づいて、学内公募によって採択された11のプロジェクトが、それぞれ助成を受けて3年計画で研究活動を推進しています。
IoT、AI、ビックデータなど情報通信技術分野における革新的研究、医療・健康福祉分野での先進国をリードする研究、SDGsの達成に貢献する研究、ポストコロナにおける各種教育の高度化に資する研究などの重点研究課題を設定し、学内研究者による研究拠点、研究グループを公募し、助成を行い、研究を進めています。







