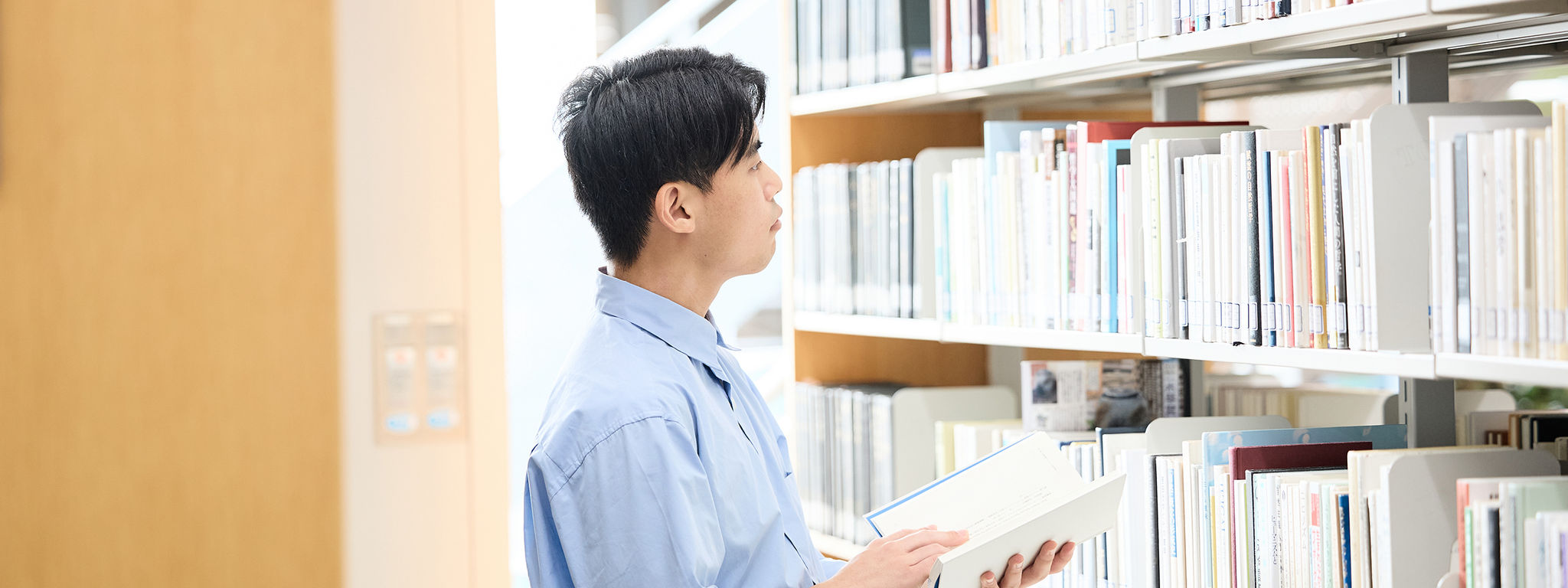商品企画・開発、広告宣伝、流通。これらを連携させて「売れる仕組み」をつくる「マーケティング」について、各専門分野を体系的に学びます。感性と科学的なデータ分析力を磨き、魅力的なマーケティング戦略を企画・立案・実行できる人材を目指します。
高い感性とデータの力で、新たな価値を創造する。
学問の魅力
実践的なマーケティング戦略の構築方法を学ぶ
マーケティングとは、消費者の欲求を敏感に読み取り、そのニーズを満たす商品やサービスを開発して提供すること、つまり「売れる仕組み」をつくる一連のプロセスのことです。
身近な商品やその広告の魅力を学問的に解き明かしたり、環境問題や高齢化など、社会が抱える課題の解決に向けたアプローチを検討したりなど、実社会とマーケティングの関わりを実感しながら学びを展開。理論を学び、ビッグデータを分析・活用するスキルも身につけながら実践を繰り返すことで、実社会でも活かせるマーケティング力を培うことができます。
学びのメソッド
マーケティングの学びに必須の「3S」を身につける
マーケティングを学ぶ上で特に重要な要素が、①マーケティングセンス(Sense)、②サイエンス(Science)、③戦略(Strategy)の「3S」です。本学科ではこの「3S」を身につけ、戦略的な発想で企画、立案、実行ができるスキルの獲得を目指します。
マーケティングセンスの基本には、常に顧客視点で問題を考える姿勢があります。情報感度を高め、市場や顧客が求めているもの・必要としているものについて敏感であることも欠かせません。サイエンスとは、客観的なデータを分析することによって現実の事象を理解し、その本質を捉えようとする視点です。マーケティング理論を応用しながら、優れたマーケティングセンスとサイエンスに基づいた、効果的なマーケティング戦略の立案・実行ができる人材を目指します。
ビッグデータ分析や先端的理論も学べるカリキュラム
マーケティングの基礎を固める
1年次の科目「基礎実習講義」では、マーケティングの基礎知識を学びます。さらに「マーケティングデータ分析入門」では「重回帰分析(一つの結果に対して、複数の原因がどのように影響しているかを分析する手法)」の習得を目標に、データ分析の基礎を身につけます。
データの分析力をさらに磨く
ビッグデータの活用がマーケティング戦略に欠かせないアプローチの一つとなっていることから、本学科では「ビッグデータ時代のサイエンス教育」を重視しています。「現代のマーケティング・サイエンス」や「現代のマーケティングデータ分析」といった科目では、「多変量解析(複数のデータの関係性からある現象の原因や仕組みを調べる、統計学の手法)」をはじめ、様々なデータをマーケティング戦略に活かすための高度なデータ分析手法を学ぶことができます。
3つのコースで専門性を高める
それぞれの興味や得意分野に応じてより専門的な学びを深められるよう、本学科のカリキュラムには「マーケティング戦略コース」「マーケティング・サイエンスコース」「流通・サービスマーケティングコース」の3つのガイダンスコースが設けられています。
特に演習(ゼミナール)など少人数制の研究活動の場では、それぞれが主体的に研究に打ち込み、自由な発想でお互いに刺激しあいながら学びを深めます。大学の内外で研究成果を発表したり、議論したりする機会も充実しています。コミュニケーションスキルやビジネススキルを育むことができます。
実社会で通用する、実践的なマーケティング力を培う
専門領域を持つ先生方のバラエティ豊かな指導を受けながらマーケティングを学び、4年次には学習と研究の成果を卒業論文としてまとめ上げます。社会に出てから活用できる、実践的なマーケティング力を培うことが目標です。
「教育課程表」には、本学科が設置している科目を掲載しています。「カリキュラムマップ」では各科目をテーマごとに分類し、それぞれの科目がどのように関わり、つながっているかを紹介しています。
卒業論文のテーマ例
- テレビドラマ連動型広告の効果
- アパレル商品購買におけるインフルエンサーと消費者の関係について
- 待ち列の効果とその活用〜行列形態の比較による活用場面の考察〜
- 神対応が消費者に与える影響 クチコミ意向および満足度に着目して
- Z世代におけるインフルエンサーの影響力と購買意向の関係―フォロワー数が低関与商品に与える影響―
学びのポイント
主体的な取り組みでマーケティングを学ぶ
「ゼミナール(ゼミ)」では、マーケティング分野を専門領域とする指導教員のもとで、研究調査に取り組みます。各教員の専門によりゼミのテーマが異なることから、自分の興味や志向に応じて所属ゼミを選択します。
ゼミ生同士の共同研究や発表・討論、ゼミ合宿、それら成果を対外的に発表する「1部経営学会」での研究報告、他大学ゼミとの討論会、研究発表大会など、ゼミでの取り組みはいずれも学生による主体的な学習への取り組みを前提に行われています。それを支えるマーケティング分野の多彩な専門科目があります。
仲間との関わりを深めながら調査研究に取り組む
所属するゼミの選択は、1年生の秋学期に開催される「ゼミ合同説明会」などを参考に行います。
合同説明会では各ゼミのテーマや特徴などが説明されるほか、ゼミによっては個別の説明会や、オープンゼミ(体験ゼミ)なども行われます。
ゼミでの学びは少人数で行われることから、教員・先輩・後輩との関わりが深くなり、生涯の友との出会いを得られるのも醍醐味です。
約100チームが研究発表!「1部経営学会研究大会」
経営学部の学生および教員から組織される「1部経営学会」では、学生が主体となってイベントなどの運営にあたり、研究発表大会、講演会、卒業生交流などが行われています。特に「1部経営学会研究発表大会」では毎年、約100ものグループが研究報告を行い、活発な討論が繰り広げられています。
ゼミのゴールは卒論作成。表彰も。
ゼミでの学びのゴールは、一人ひとりが4年次に取り組む卒業論文にあります。優秀な卒業論文には、経営学部卒業論文賞、校友会学生研究奨励賞が贈られます。

入試イベントや過去問対策、出願登録まで、メンバー限定のお得な特典をゲットしよう!