【SDGs NewsLetter】脳の多様性(ニューロダイバーシティ)への理解を高め、QOL向上につなげる
SDGs NewsLetter
SDGs
NewsLetter
vol.7
東洋大学は“知の拠点”として
地球社会の未来へ貢献します
2022.03.23発行


脳の多様性(ニューロダイバーシティ)への理解を高め、QOL向上につなげる
本ニュースレターでは、東洋大学が未来を見据えて、社会に貢献するべく取り組んでいる研究や活動についてお伝えします。
今回は、生命科学部生命科学科の金子律子教授に、脳科学の視点から考える人々の健康やQOL(生活の質)について聞きました。
summary
- ニューロダイバーシティはすべての人に当てはまる概念
- 動物の脳メカニズム解明を人間の神経回路再生技術に生かす
- すべての人の健康とQOL向上のために
ニューロダイバーシティはすべての人に当てはまる概念
研究のテーマとして掲げている「ニューロダイバーシティ(neurodiversity)」について教えてください。
「ニューロダイバーシティ」は「人のさまざまな神経疾患は、通常のヒトゲノムとの違い(変異、差異)が結果として現れている」という意味で使われることが多いです。しかし、脳の発生、発達、老化を科学的視点から見た場合、そもそも「理想的な脳の神経回路」というものは存在しません。脳の神経回路は誰もが少しずつ異なるので、ニューロダイバーシティは何かしらの神経障がいや疾患を有する人を対象にしているのではなく、「脳の多様性」を表す言葉としてすべての人に当てはまる概念だと言えます。
この分野に興味を持ったきっかけは、大学院時代に自閉症の子どもたちのボランティアを経験したことでした。その後、生命科学の研究者として脳のあるタンパク質に注目して研究を進めていた中で、そのタンパク質の遺伝子(DNA)のたった一つの塩基の変異によって自閉症スペクトラム障がい(ASD)が発症したと考えられる患者さんを共同研究により見出しました。その後、そのタンパク質(CRMP4)の機能や、変異や欠損による影響をモデル動物を使って調べました。そして更に、臨床心理学や幼児教育といった分野も学びつつ、ASDを中心に発達障がいの発症メカニズムや早期支援の方法について、脳科学の視点から研究しています。
ASDの研究はどのように進めていますか。
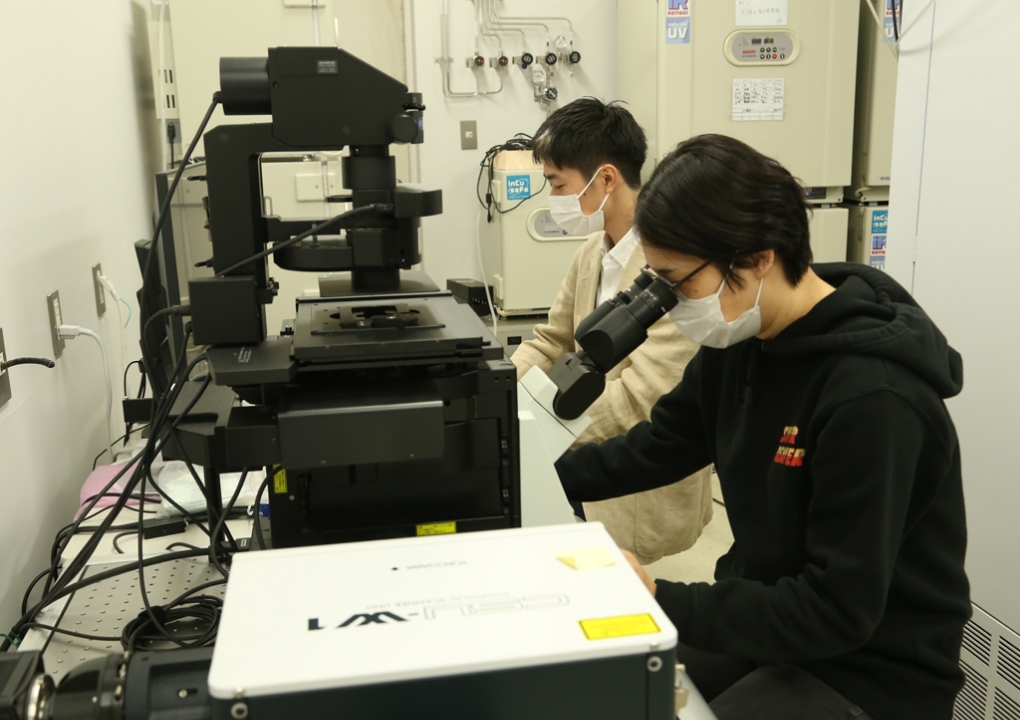
全発現遺伝子解析により、男児ASD患者に変異遺伝子を見出したのですが、この患者さんの場合、発症に関係していると考えられたのはCRMP4というタンパク質の遺伝子の一塩基変異でした。その後の研究で、CRMP4が変異したり欠損すると、ニューロンの形態が変化することが分かりました。またCRMP4欠損マウスでは、ASDに特徴的な社会性行動の低下や感覚異常などが現れました。ASDの発症率には顕著な性差があることが知られていますが、CRMP4欠損マウスでみられるASD様の特徴にも性差があります。今後もCRMP4に注目しながら、ASDの発症メカニズムを研究していく予定です。
現在、医大付属病院精神科でASD患者さんの感覚特性に関する調査にも関わっています。ASD患者さんの中には、感覚が極端に鋭いあるいは鈍いために生活に不自由さを感じている方が多くいます。例えば、気温に合わせて衣服の着脱をするのが苦手な方などです。患者さんの声を聴きながら、これまであまり調べられてこなかった温度感覚についても調査しています。また乳幼児期の感覚特性に着目した早期発見や支援についても研究を始めています。ASD患者さんの生き辛さの改善・支援に繋がるような調査研究が行えればと考えています。
動物の脳メカニズム解明を人間の神経回路再生技術に生かす
人間の脳だけでなく、魚など動物の脳も研究されているそうですね。
人間を含む哺乳類は出生時に身体的な性が決まり、出生後もその身体的な性が維持されますが、動物のなかには性の可塑性が高いものもいます。例えば魚では、成長や環境に応じて自ら性転換する種や、人為的なホルモン注射などによって生殖腺(卵巣や精巣)が性転換する種がいます。生殖腺が性転換する動物では、転換した生殖腺に合わせて生殖行動も変わります。つまり脳の性転換も同時に起きます。私たちが調べているティラピアという魚は、雌雄で生殖行動が全く違います。オスは産卵のための巣穴作りを行い、メスの親は受精卵から仔魚までを口の中で育てます。メスに雄性ホルモンを注射すると、巣作りをしないはずのメスが巣穴を掘るようになります。このとき、メスの脳である特定のニューロンが変化していることを発見しました。さらにニューロンの変化(神経回路改変)のメカニズムについても徐々に明らかにしています。魚の脳の性転換に伴う神経回路改変メカニズムの解明は、将来的には人間の神経回路の再生技術の開発へとつながる可能性があります。
すべての人の健康とQOL向上のために
今後、先生の研究はどのように生かされていくのでしょうか

すべての人が健康に生活することのできる未来に貢献していきたいと思いますが、まずはASD患者さんの感覚特性についての調査研究やメカニズム解明を通して、ASD患者さんの支援に繋げたいと考えています。ASD患者さんの感覚特性はとても多様で一人一人異なっていますが、感覚の違いは周りの方から理解され難いものです。また感覚の違いは乳幼児期の育てにくさに繋がり、愛着形成がうまくいかない等の二次的な問題が生じてしまうこともあります。「すべての人が一人ひとり異なる脳の神経回路を持っている」というニューロダイバーシティの概念を多くの方に理解していただき、脳科学の視点を障がいや疾患を抱える方々の保育・教育や支援活動に生かし、SDG4が示す「質の高い教育をみんなに」の実現に貢献していきたいと考えています。
多種類のホルモンや免疫系の生理活性物質あるいは遺伝子変異など、様々な体内の要因が脳の機能に影響を及ぼしています。また物理化学的な対外環境の影響、あるいは虐待などの人間関係も脳の発生・発達に大きな影響を及ぼすことが明らかになっています。脳の発生や発達を総合的に捉え、医学、臨床心理学、保育など他分野の研究者や現場で活躍する方々と連携しながら、研究を進めたいと考えています。

金子(大谷) 律子(かねこ(おおたに) りつこ)
東洋大学 生命科学部生命科学科 教授
専門分野:脳神経科学、神経発生学、神経解剖学、内分泌学
研究キーワード:脳の発生・発達、自閉症スペクトラム障害、脳の性分化、脳の性転換
















