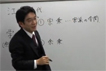Research 国際哲学研究センター
※当センターは、活動を終了しました。
About
今日の多元化した地球社会の諸問題を
自覚的に捉え、問題解決型の哲学研究を推進します。

本センターは、2011~2015年度文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に選定されました。
2016年度に「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブと統合し、2019年度から2021年度まで東洋大学重点研究推進プログラムに採択され、活動いたしました。
国際哲学研究センター長挨拶
- センター長挨拶
-
国際哲学研究センターの研究テーマは、時代の動向を反映して、大幅に変更を迫られることになった。AIや情報科学の予想外の急速な進展によって、時代の局面が見通しの効かないほど変化してきたのである。
そこでテーマ領域として、(1)情報科学技術社会、(2)エコ・フィロソフィー、(3)共生思想、(4)哲学史の大枠でのプログラムの設定を行った。ここでの変更は、多くの学部からの参加を見込めるかたちにすることと、全学総合のプログラムとして、やがて各キャンパスをつなぐテレビ授業へと展開するために、新たなプログラムを設定すること、さらには既存のプログラムの力点を変えていくことである。これらは国際哲学研究センターの活動を支援してくれる学長やそのスタッフの希望を受けてのものでもある。共生思想の網羅的な研究や哲学史の研究は、息の長い研究で、本来5年10年と続けていくもので ある。たとえ小さな研究会であっても、息長くやっていくべきものである。これらもどこかで局面が変わっていくことがあるかもしれない。そのときには、力点を変えて重点的に進めていくことになる。さしあたり同時代のなかで、なにかが出現するとき、哲学は何をなしうるかというのは、いつも生じてしまう課題である。たんなる評論家であってはいけない。また歴史的に距離の取ることのできるテーマでもない。当初からどうすればよいかが決まっているのでもない。同時代のテーマは、たんに論じるだけではなく、この動向になんらかのかかわりを持ってしまう。どんなにささやかであっても、テーマそのものに影響を及ぼすところまで立ち入ることが必要となる。だがそのことによって、同時代の動向に巻き込まれないでいることはほぼ不可能である。こういう場面で、試行錯誤を繰り返すことが、プログラムの特質でもある。今年度は、こうした試行錯誤の1年だったと思う。河本 英夫
The research topics of the International Research Center for Philosophy have been compelled to change dramatically, reflecting the trends of the times. Along with the unexpected rapid progress of AI and information science, the current situation has changed to a degree where predictions are impossible.
Therefore, as subject areas, we have broadly established programs under the framework of (1) information science and technology society, (2) eco-philosophy, (3) thoughts for harmonious coexistence, and (4) history of philosophy. These changes are necessary to establish new programs and changes in the existing programs, to facilitate participation by individuals from other departments as a comprehensive university program, and to eventually develop into television lectures linking each campus. These are also based on the request of the university president and staff members who support the activities of the International Research Center for Philosophy. Comprehensive research on thoughts for harmonious coexistence and researches on the history of philosophy are long-standing research projects that will continue for 5 and 10 years, respectively. Although the projects comprise small study groups, we should continue for an extended period. However, there may be times when conditions change again. At that time, we will focus on altering the research emphasis. When an issue emerges during a certain period, it is always necessary to examine what philosophy can do at that moment. Philosophers must not be mere critics. Moreover, there are no topics for which a historical distance can be created. From the beginning, there is no definitive method on what should be implemented. Contemporary themes are not merely debate topics, but also have some involvement in trends. No matter how trivial the theme’s impact may be, it is necessary to engage where it affects the theme itself. However, it makes it almost impossible to track the trends of the same era. Given this background, repeated trial and error is also a program characteristic. I believe that this year was a year of such trial and error.Hideo Kawamoto
センター紹介
- 研究センターの目的
-
本センターは、伝統的な哲学研究に中心軸を据えつつも、変容を早める科学技術や国際情勢に正対し、東洋大学の創設者である井上円了が志したように、哲学的活動とその成果をこれからの社会に還元させることを目指ざしています。哲学研究という営み自体を反省する一方で、芸術、医療、工学といった多分野との学際的交流を通じ、社会からの哲学に対する潜在的な期待や要請を把握することで、次世代に向けた哲学のあり方を広く提案します。
- 研究センターの活動
-
本センターは「哲学・哲学史」「環境」「情報技術」の3グループから成ります。哲学・哲学史グループは、哲学研究を遂行しながら、その研究方法自体を批判的に検討します。環境グループは、最先端の知見がもたらす多様な「環境」概念から把握される新たな人間像を析出します。情報技術グループは、ロボットやAIの社会実装に必要な倫理的設計デザインの枠組みを模索します。
- 研究センターの展開
-
各グループの研究成果を社会に還元するために、シンポジウムやワークショップを開催していきます。また、そのような活動を通じ、これからの社会において哲学が扱うべき課題を共有し、より有意義で実りある研究成果を発信していきます。
- 2011年度~2015年の国際哲学研究センター研究ユニットについて
-
第1ユニット
日本哲学の再構築に向けた基盤的研究
井上円了及び近代日本の哲学研究ユニットでは、日本近代以降の哲学受容史をふり返りつつ、その日本的特質を分析・究明することを通して、日本近現代哲学の独創性を探究すると同時に、さらには、その営みが今後の地球社会を先導する先進的な価値観の創造にどのように寄与しうるかを、国際的な連携の中で考察する。特に、本学の創立者である井上円了の業績の本格的な研究は、本学における建学の理念を正しく自覚するためにも、急務であると考える。
また、同時代の哲学者には、西周、井上哲次郎、ら何人かの先駆的「哲学」者がいるが、これらの「哲学」者も含めて、幕末から明治にかけての時代、ウエスタン・インパクトを受け、伝統的価値観と普遍的価値観との衝突の中で、どのように哲学研究を行い、独自の思索を展開してきたのかをあらためて検証し、その姿勢に学ぶことは、今日のグローバル時代を生き抜いていく上に大きなヒントを与えてくれるであろう。
具体的な研究の視点としては、井上円了研究だけでも、
- 井上円了の思想形成史の解明
- 井上円了の哲学の核心の究明
- 井上円了における哲学と仏教の関係の究明
- 井上円了の哲学と同時代の哲学思想との関係の究明
- 井上円了の哲学および同時代の他の哲学の継承すべき点の分析
等々がある。東洋大学には、その後、大内青巒、境野黄洋らが出て、円了の思想を継承していった。その状況を追跡するとともに、その他、西田幾多郎、田辺元、和辻哲郎、九鬼周造等、日本近現代の哲学の営みに固有の特質をも究明していく。これらの研究を丹念に進めて行く中で、日本近代哲学史を新たに書き直す作業をも果したい。
以上のように、西洋スタイルの哲学研究を開始した時代から、日本人はどのように哲学の営みを遂行してきたのかをあらためて検証することによって、かえって将来の日本の哲学研究の進むべき進路を展望することを目指す。また、その研究成果を他の研究ユニットに提供し、あるいは、対話することによって、混迷を深めている地球社会に対し、新たな哲学の方法論と価値観とを産み出すことが可能となるであろう。それらを国際的に発信することにより、地球市民のライフスタイルの革新やコミュニティの再生をもたらし、多元化社会のそれぞれの伝統の尊重と連帯・統合とを果すことができよう。
第2ユニット
東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究
本研究は次の二点を骨子とする。(1)あらゆる思考が差異を保ちつつ交流し合う方法の確立を目指すこと、(2)多様な国語相互の差異がその文化の差異の反映であることを見失うことなしに研究が交流される仕組みを明らかにすることである。
- 東洋大学の哲学的伝統を培ってきた井上円了以来の知的資源を東西哲学・宗教と連接しようとする「第1のテーマ」と連携しつつ、東西哲学・宗教の根幹をなすさまざまな立脚点を統括的に論じうる議論場・ロゴスの場を形成するために、諸外国の哲学・宗教研究者と普段に討論のできる仕組みの構築を目指す。それによって、あらゆる哲学・宗教的思考が差異を保ちつつ交流し合うことのできる方法論の確立に向けて研究を進める。その際、哲学の方法論とは、学際的研究による他の諸個別科学の方法論をも包括的な批判的検討にもたらしうる学問一般の方法論の基幹たる特性をもちうるのでなければならない。
- また、その際、諸言語の多様性にかかわる語彙・文法構造と思索様式との密接な連関が考慮されねばならないだけでなく、諸文化における知覚と言語との相互の関係の仕方の差異と共通性が研究されねばならない。ということは、諸文化の核心をなす感じ方と考え方の多様性を保ちつつ、相互に交流することによってこそ、多様性と共生との稔りある総合が可能になるのである。このためには感性との相互関係における言語的把握の多様性を喪失することなく、育成しつつ、文化の核心とその結晶ともいえる哲学的思考を世界規模において交流する仕組みを明らかにすることが肝要である。これを実現するために、複数の二カ国語の間(まずは、われわれの文化形成の基盤になってきた、日・仏、日・独、日・中、日・韓)での双方向的な思索の即時的交流を可能にする翻訳者を養成することが目的とされる。
第3ユニット多文化共生社会の思想基盤研究
本研究ユニットは、文化的多様性や宗教的多様性が現代社会にもたらす諸問題を、哲学、宗教学の視点から捉え直し、「共生」すなわち共に幸福に暮らしていける思想基盤を探ることをテーマとする。近年、社会のさまざまな問題に絡めて「共生」という語が多用されるようになった。いまだ統一的な定義や概念はないものの、この言葉は、抑圧や差別、対立や不平等、一方的な支配や侵害を超えて、「自立と連帯のなかで、誰もが十全に自己実現を果たすことが可能な社会」(竹村牧男ほか編『共生のかたち』誠信書房、平成18年、p.7)を目指すといった意味合いで使用されていると考えられる。「共に生きる」という人間や社会の在り方は、利潤追求とは対極の幸福を第一に考える人生観・世界観を前提にしなければ成り立たない。しかしその「幸福」も、誰にとっての幸福かを考えると、そこには多くの難題が表出する。
西洋に端を発する一元的な価値観や合理主義、および市場経済のグローバル化に直面した現代社会において、人間の根本的生き方が問われる「共生」について考えることは、今取り組むべき喫緊の課題であると言えるであろう。また、本研究は共生を中心的なキーワードとしつつも、人権、公共哲学、民主主義、等のテーマも共に扱っていくものとする。
本研究はオープン・リサーチ・センター事業として平成18年度より5年間活動してきた東洋大学共生思想研究センターの成果を踏まえつつ、より広範なテーマに取り組み、新たな世界秩序の構築に資する制度設計デザインを追及する。具体的な研究視点としては、
- 多文化社会における個人あるいは集団のアイデンティティー認識あるいは帰属意識の問題究明
- 異民族間の共生の問題
- 異宗教間の共生の問題
- 多言語使用国家・地域における構成員間の交流の問題
- 人間と自然・環境との共生
等を考えている。以上のような歴史的、地理的、文化的にも多様な領域にまたがる問題を、国内外の研究者の複数の視点から考究・検討することにより、今後の世界展望を共に考えていきたい。
2015年度までの「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブの研究ユニットについては こちら をご覧ください。
- 自然観探究ユニット
- 価値観・行動ユニット
- 環境デザインユニット
2021年度構成員紹介
活動報告
- 共同研究
-
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)社会技術研究開発センター(RISTEX)委託事業との共同研究
国際哲学研究センターは、2018年度より、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)社会技術研究開発センター(RISTEX)委託事業戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発)「人と情報のエコシステム」研究開発領域研究開発プロジェクト「自律機械と市民をつなぐ責任概念の策定」(平成29年度採択:平成29年10月~平成32年9月)と共同研究を行います。
1995年8月31日に、東洋大学と韓国東国大学校は、「交流に関する協定書」を締結いたしました。この学術交流を具体化するために、2014年5月1日に、国際哲学研究センターと東国大学校仏教大学が共同研究に関する協定を締結いたしました。
この協定に基づき、2年間にわたり、韓国と日本で2回ずつ、計4回の共同セミナーを開催いたします。
- 2011年度~2015年度 研究成果報告書
-
S1191005 国際哲学研究センターの形成――多元化した地球社会における新たな哲学の構築
平成23年7月1日に文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成事業」に採択されたプロジェクトの研究成果です。
動画集
このページでは、国際哲学研究センターが開催した研究会・シンポジウムなどを収録した動画を公開しています。
- 動画集
-
第2ユニット「方法論シンポジウム:哲学の方法としての翻訳の意義」(2015年2月28日開催)
2015年2月28日、東洋大学白山キャンパス2号館スカイホールにおいて、方法論シンポジウム『哲学の方法としての翻訳の意義』が開催されました。今回のシンポジウムでは、発表者として新『アリストテレス全集』の翻訳者である中畑正志氏(京都大学)、神崎繁氏(専修大学)を、特定質問者として土橋茂樹氏(中央大学)をお迎えしました。
第1ユニット「明治期における人間観と世界観」西村玲氏研究会(2015年1月14日開催)
第1ユニットでは「明治期における人間観と世界観」と題した連続研究会を行っています。今回は、西村玲氏による「釈迦仏からゴータマ・ブッダへ ―釈迦信仰の思想史」と題した研究会を開催しました。
第2ユニット「ポスト福島の哲学:原発事故後のエネルギーと本当の豊かさ」(2014年11月22日開催)
11月22日、東洋大学白山キャンパス6号館6302教室において、「ポスト福島の哲学」シンポジウム「原発事故後のエネルギーと本当の豊かさ」が開催され、国際環境NGOグリーンピース・ジャパンの高田久代氏と、「なないろの空」代表の村上真平氏による講演が行なわれました。
村上勝三教授 最終講義「超越の方法―デカルトの途」(2014年10月25日開催)10月25日、東洋大学白山キャンパス6号館6312教室にて、第2ユニット「方法論」研究の講演会として「村上勝三先生最終講義:超越の方法―デカルトの途」が開催されました。
Web国際会議「理性と経験―スピノザ哲学の方法―」(2014年10月11日開催)
10月11日、東洋大学白山キャンパス8号館特別会議室において、4回目となるWeb国際会議「理性と経験―スピノザの方法について」をテーマに開催しました。この会議は日本とフランスをインターネットで結んで行なわれ、フランス高等師範学校リヨン校のピエール‐フランソワ・モロー氏に参加いただきました。そして日本側からは、特定質問者として大西克智客員研究員(熊本大学)、渡辺博之客員研究員、藤井千佳世氏(日本学術振興会特別研究員)、そして村上勝三研究員(東洋大学文学部)が司会を務めました。
第1ユニット「明治期における人間観と世界観」出野尚紀氏研究会(2014年10月8日開催)
第1ユニットでは「明治期における人間観と世界観」と題した連続研究会を行っています。今回は、出野尚紀氏による「明治期と自然災害」と題した研究会を開催しました。
国際哲学研究センター全体シンポジウム「国際化とは何をすることなのか~東洋大学国際哲学研究センターの「これまでとこれから」~」(2014年9月24日開催)
2014年9月24日、東洋大学白山キャンパス5号館5404教室にて、全体シンポジウム「国際化とは何をすることなのか~東洋大学国際哲学研究センターの「これまでとこれから」~」が開催されました。このシンポジウムは、センター最終年度を来年度に控えた4年目である本年に、センターのこれまでの成果と今後の展望を報告すべく、3つのユニット合同で行われました。
国際井上円了学会 第3回学術大会 特別講演:ウルリッヒ・ジーク「大なる総合を求めて―1900年頃の哲学」(2014年9月13日開催)
2014年9月13日、東洋大学白山キャンパス8号館125記念ホールでの国際井上円了学会第3回学術大会において、ウルリッヒ・ジーク氏(マールブルク大学教授)による、「大いなる総合を求めて―1900年頃の哲学」と題された特別講演が行われました。
第1ユニット研究会「善の曖昧さ―精神の戦争におけるドイツ人の教授達―」ウルリッヒ・ジーク氏研究会(2014年9月10日開催)
2014年9月10日、東洋大学白山キャンパス6号館第3会議室にて、ウルリッヒ・ジーク氏(マールブルク大学)による「善の曖昧さ―「精神の戦争」におけるドイツ人の教授達―」と題された第1ユニットの研究会が開催されました。
第1ユニット「明治期における人間観と世界観」岡田正彦氏研究会(2014年7月9日開催)
第1ユニットでは「明治期における人間観と世界観」と題した連続研究会を行っています。今回は、岡田正彦氏による「梵暦運動史の研究―19世紀の日本における仏教科学の展開―」と題した研究会を開催しました。
第1ユニット「明治期における人間観と世界観」吉田公平氏研究会(2014年6月11日開催)
第1ユニットでは「明治期における人間観と世界観」と題した連続研究会を行っています。今回は、吉田公平氏による「心学の変身 西田幾多郎の「修養」と「研究」、夏目漱石「こころ」の苦悩」と題した研究会を開催しました。
第2ユニット「ポスト福島の哲学」堀切さとみ氏講演会(2014年5月30日開催)
第2ユニット「ポスト福島の哲学」、2014年度第1回目は、ドキュメンタリー映画「原発の町を追われて」の上映会を行いました。映像は、上映後に行われた本映画の制作者である堀切さとみ氏による講演です。
第2ユニット「方法論研究会」山口祐弘氏研究会(2014年4月19日開催)
第2ユニット「方法論研究会」2014年度の第1回目は、山口祐弘氏による「ドイツ観念論の課題と方法―近代哲学の超克に向けて―」と題した研究会を行いました。
第2ユニット「方法論研究会」河本英夫氏研究会(2014年3月1日開催)
第2ユニット「方法論研究会」、2013年度最後となる第5回目では、河本英夫氏の「方法としてのオートポイエーシス」と題する発表を行いました。
第1ユニット研究会「近世排耶論の思想史的展開 ──明末から井上円了へ──」(2014年1月15日開催)
第1ユニットでは、公益財団法人中村元東方研究員専任研究員である西村玲氏を迎えて、「近世排耶論の思想史的展開 ──明末から井上円了へ──」と題する研究会を行いました。
第3ユニット研究会マルクス・ガブリエル氏連続講演会(2013年12月17・18日開催)
第3ユニットでは、ボン大学教授であるマルクス・ガブリエル氏を招聘し、2013年12月17、18日の2日間に渡って講演会を行いました。1日目は"Die Ontologie der Prädikation in Schellings Die Weltalter"、2日目は"Die Zeitphilosophie in Schellings Weltaltern"と題した講演会となっております。
第2ユニット研究会「ポスト福島の哲学」山口祐弘氏研究会(2013年12月14日開催)
第2ユニット「ポスト福島の哲学」、2013年度第5回研究会「核時代の生 ―哲学・思想からの提言―」(2013年12月14日開催)、山口祐弘氏の研究会の動画です。
Web国際会議「合理主義者と経験主義者による哲学の方法についての対話」(2013年10月12日開催)
2013年10月12日に東洋大学国際哲学研究センター主催でWeb国際会議「合理主義者と経験主義者による哲学の方法についての対話」が開催されました。総合司会はIrcpの山口一郎が務め、各人の発表・コメント・討議を行いました。フランスからはエドゥアール・メール(ストラスブール大学)氏が"Le problème de l'idéalité du monde extérieur"「外的世界の観念性という問題」と題した発表を行いました。また、イギリスからはヘレン・ビービー(マンチェスター大学)が"Hume on inductive skepticism"「ヒュームの帰納的懐疑主義」を発表しました。この後、日本側から村上勝三(Ircp)、一ノ瀬正樹(東京大学)がそれぞれにつてコメントしました。
第2ユニット研究会「ポスト福島の哲学」納富信留氏研究会(2013年10月5日開催)
第2ユニット第3回研究会「ポスト福島の哲学」、「「理想」を論じる哲学――ポスト福島の今、何を語るか」(2013年10月5日開催)、納富信留氏の研究会の動画です。
第1ユニット研究会「三宅雪嶺の哲学――儒教心学再生の試み」(2013年7月10日開催)
第1ユニット第2回研究会「三宅雪嶺の哲学――儒教心学再生の試み」(2013年7月10日開催)の動画です。渡部清氏(上智大学名誉教授)による講演です。
第3ユニット国際シンポジウム「共生の哲学に向けて――言語を通じて古代アジアの人々の価値観を探る」(2013年6月22日開催)
第3ユニット国際シンポジウム「共生の哲学に向けて――言語を通じて古代アジアの人々の価値観を探る」(2013年6月22日開催)の動画です。後藤敏文氏氏(東北大学名誉教授)による講演「インド・アーリヤ諸部族の背景とインド文化、そして現代」です。
第1ユニット研究会「開堂初期に哲学堂を訪れた人々」(2013年6月12日開催)
第1ユニット第1回研究会「開堂初期に哲学堂を訪れた人々」(2013年6月12日開催)の動画です。出野尚紀客員研究員による講演です。
第2ユニット研究会「ポスト福島の哲学」高橋真樹氏講演会・映画上映会(2013年5月17日開催)
第2ユニット主催の連続企画「ポスト福島の哲学」の2013年度第1弾として、映画『第四の革命 エネルギー・デモクラシー』の上演の後、フリー・ライターの高橋真樹氏映画監督に講演をしていただきました。
第1ユニット研究会「井上円了の相含論とスピノザ主義」(2013年3月14日開催)
第1ユニット第8回研究会「井上円了の相含論とスピノザ主義」(2013年3月14日開催)の動画です。小坂国継客員研究員(日本大学経済学部)による講演です。
第2ユニット研究会「ポスト福島の哲学」村上勝三(2013年3月12日開催)
第2ユニット第5回「ポスト福島の哲学」(2013年3月12日開催)。村上勝三研究員による講演です。
第1ユニット研究会「井上円了における伝統仏教教学体系と仏教・哲学一致論」(2012年11月28日開催)
第1ユニット第5回研究会「井上円了における伝統仏教教学体系と仏教・哲学一致論」(2012年11月28日開催)。佐藤厚客員研究員による講演です。
Web国際講演会「日本における漢学と西学-中江兆民を中心に-」(2012年11月14日開催)
Web国際講演会「日本における漢学と西学-中江兆民を中心に-」(2012年11月14日開催)。吉田公平研究員(東洋大学文学部教授)による講演です。ストラスブール大学日本学科と共同で、日本とフランスを繋いで行なわれました。
第2ユニット研究会「ポスト福島の哲学」鎌仲ひとみ監督講演会(2012年10月19日開催)
第2ユニット主催の連続企画「ポスト福島の哲学」の201年度第4弾として、映画監督の鎌仲ひとみ氏に講演「『内部被ばくを生き抜く』をめぐって」を行なっていただきました。
第2ユニット研究会「ポスト福島の哲学」――保養と避難の現状――(2012年10月6日開催)
第2ユニット主催の連続企画「ポスト福島の哲学」の今年度第3弾として、実際に被災者・疎開者を支援する活動を行なっている方々を講師に招き、「保養と避難の現状」を主題とした研究会を開催しました。講師は、吉野裕之氏(「子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」)、木田裕子氏(「母子疎開支援ネットワーク「hahako」」)、疋田香澄氏(「子どもたちの健康と未来を守るプロジェクト」)の三名。
東洋大学創設125周年記念国際シンポジウム「グローバルな現実に向きあう哲学」(2012年9月16日)
東洋大学創立125周年記念行事の一環として国際シンポジウム「グローバルな現実に向きあう哲学」を開催しました。講演者はジャヤンドラ・ソーニー氏(オーストリア・インスブルック大学)、呉震氏(中国・復旦大学)、エティエンヌ・タッサン氏(フランス・パリ第7大学)、ケネス・田中氏(武蔵野大学)の四名。
東洋大学創設125周年記念「国際井上円了学会」設立大会(2012年9月15日開催)
東洋大学創立125周年記念行事の一環として「国際井上円了学会」設立大会が行なわれました。
竹村牧男東洋大学学長・国際井上円了学会会長の公開講演に続き、国内外から5名の研究者らが集い設立記念シンポジウム「国際人・井上円了」が開かれました。国際井上円了学会フランス研究集会「井上円了とその時代」(2012年6月30日開催)
2012年9月の国際井上円了学会の正式な発足に先立って、国際哲学研究センターは、2012年6月30日、フランス、コルマール近郊のキンザイムに位置するアルザス・欧州日本学研究所(Ceeja)において、同研究所およびストラスブール大学日本学科との共催のもと、国際井上円了学会フランス研究集会「井上円了とその時代」を開催しました。
第2ユニット研究会「デカルト形而上学の方法としての「省察meditatio」について」(2012年4月23日開催)
東洋大学国際哲学研究センター第2ユニット第6回研究会「デカルト形而上学の方法としての「省察meditatio」について」(2012年4月23日開催)。村上勝三研究員による講演です。
第2ユニット研究集会「テキストの地層学序説」(2012年2月20日開催)東洋大学国際哲学研究センター第2ユニット研究集会「テキストの地層学序説―上田閑照によるエックハルトのドイツ語説教86解釈をめぐる問題群を手がかりにして―」(2012年2月20日開催)。黒田昭信客員研究員(セルジーポントワーズ大学准教授)による講演です。
第2ユニット研究会「西田哲学の方法論」(2012年2月16日開催)
東洋大学国際哲学研究センター第2ユニット第5回研究会「西田哲学の方法論— 哲学の方法としての「自覚」と諸科学の方法としての「行為的直観」 —」(2012年2月16日開催)。黒田昭信客員研究員(セルジーポントワーズ大学准教授)による講演です。
Web国際講演会「ポスト福島の哲学―知の巨匠に尋ねる―」(2011年12月17日開催)
平成23年12月17日18時より、Web国際講演会「ポスト福島の哲学 知の巨匠に尋ねる」が行われた。今回の講演会ではインターネットを通じてフランス(ストラスブール大学)、ドイツ(ミュンヘン大学)、日本(東洋大学)を結び、フランスからジャン=リュック・ナンシー氏がフランス語で、ドイツからベルンハルト・ヴァルデンフェルス氏がドイツ語で講演を行ないました。日本からは山口一郎研究員と西谷修氏(東京外国語大学大学院教授)がコメンテーターとして参加、村上勝三センター長の総合司会のもと講演会が進行しました。
Web国際会議(2011年10月15日開催)
本会議は3ヵ国語(日・仏・独)で開催されました。映像はそれぞれの言語によるものです。なお、同時通訳は下記PDFのように行われました。
発表者紹介、会議の趣旨(Part1)[PDFファイル/248KB]
カンブシュネル教授の発表(Part2-3)[PDFファイル/282KB]
大西客員研究員からのカンブシュネル教授への特定質問(Part4)[PDFファイル/129KB]
シュテンガー教授の発表(Part5-7)[PDFファイル/301KB]
稲垣研究員からシュテンガー教授への特定質問(Part8-9)[PDFファイル/146KB]
全体討論(Part10-12)[PDFファイル/228KB]
報告書・出版物
当センターで刊行している各種年報は、創刊号から最新号まで「東洋大学学術情報リポジトリ」にて公開される運びとなりました。
閲覧およびダウンロードにつきましては、そちらをご利用くださいますようお願い致します。



















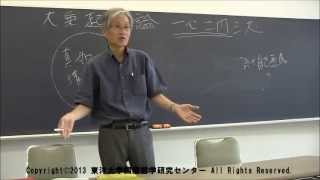
.jpg)
.jpg)