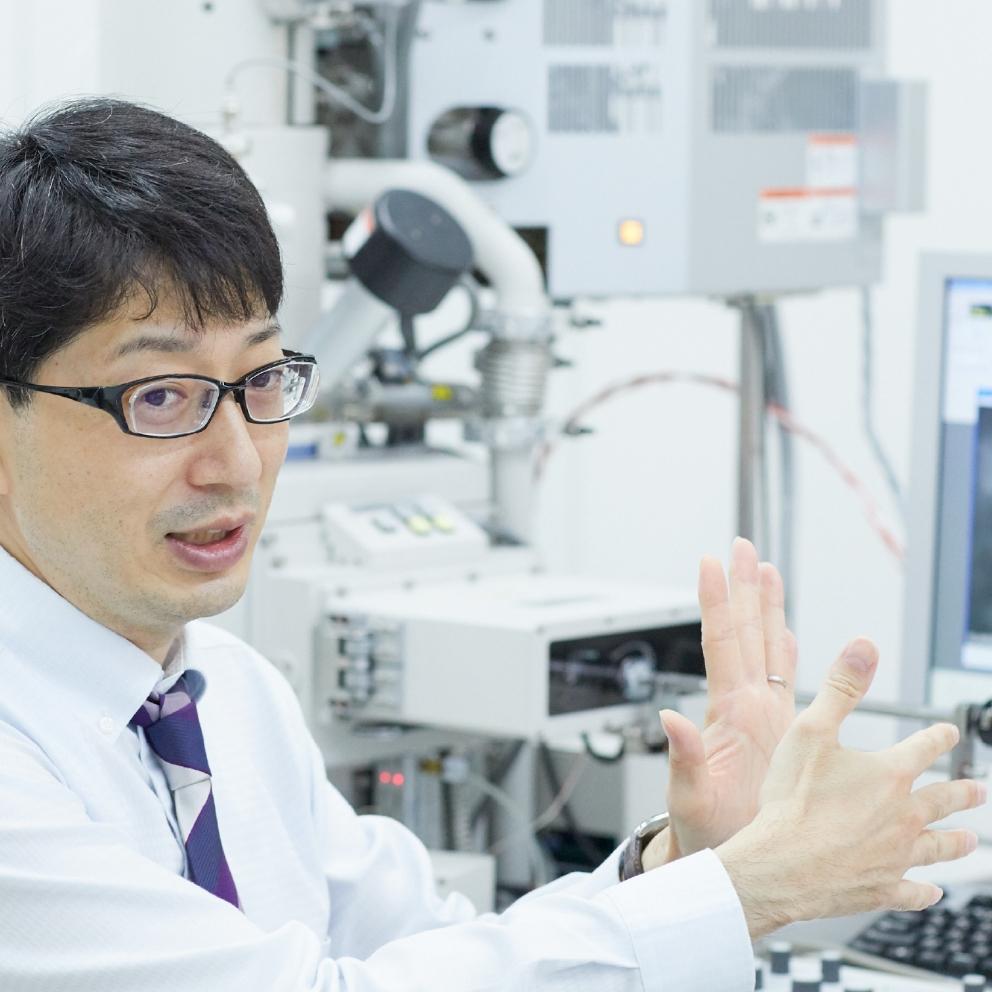我々の身体は、微小な物質が原因で病気になることがある。また、病気にかかることで正常時には見られない微量の生体物質が体内で発生することが知られている。そうした物質をいち早く検出できれば、病気の早期発見・早期治療に役立てられるはずだ。しかし、多くは1メートルの10億分の1というナノスケールの分子であり、検出するのは非常に難しい。だが、理工学部電気電子情報工学科の根岸良太准教授は、ラマン散乱という物理現象を応用した新たな検出方法を開発することにより、人間の目に見えない極小の存在を捉えようとしている。
ラマン散乱という物理現象を応用して分子の構造を解き明かす
1928年、インドの物理学者チャンドラセカール・ラマンは、物質に光を照射した際に散乱された光の中に、もとの波長と異なる波長の光がわずかに含まれていることを発見した。また、その波長は照射された物質ごとに異なるため、それをもとに物質の構造を分析することが可能になった。この現象は「ラマン散乱」と呼ばれ、発見したラマンは1930年にノーベル物理学賞を受賞する。
「光と物質の相互作用を利用したラマン散乱による分光法は、分子や生体材料などの微細な分子を可視化する優れた分析技術としてあらゆる分野で応用されています。しかし、ラマン散乱光のシグナルは非常に微弱であるため、何らかの方法で増強しないと分析できるだけの感度と精度に至りません。そこで開発されたのが、私が研究対象としている『表面増強ラマン散乱』と呼ばれる技術です」
分析の対象となる分子は、通常、自由電子の集団振動によりプラスとマイナスの電荷が適度に揺らいだ平衡状態を取る。この揺らぎの大きさ、すなわち分子の電荷の偏りによる分極を大きくすると、入射する光子と分子との衝突断面積が大きくなる。この結果、ラマン散乱光のシグナルが大きく増強されることが知られている。この現象が、表面増強ラマン散乱だ。
「分子を分極させる方法として、マクロスケールとナノスケールの2つのアプローチがあります。マクロスケールでは、金や銀など金属の板を使います。分析の対象となる分子を吸着させた板に電磁波を当てると、水面に石を投げ入れたように表面に金属の自由電子によるプラスとマイナスの波が発生する『表面プラズモン』という現象を引き起こし、分子の分極を誘起します。しかし、それによりシグナルが増強されてもまだ分析に十分な強度にはなりません。そこで近年注目されているのが、非常に微視的なナノスケールの手法です」
この手法では、分子の大きさに近い非常に狭い数nm程度のギャップ、すなわちナノギャップを利用する。金属微粒子の間のギャップに分子を配置して分極させる方法が一般的だ。金属微粒子同士の距離が近いほど電場勾配が大きくなるため、極小のナノギャップでは非常に大きな勾配が発生する。その間に分子を配置すれば、より効率よく分極し、通常の数万倍レベルの非常に強い表面増強ラマン散乱のシグナルが得られる。この現象は、ホットスポット効果、あるいは局所表面プラズモン効果という名称で知られている。

意図的に作り出したナノギャップ構造が超高感度の検出技術を実現
現在、この手法を簡便に用いるための素子が開発されており、すでに市販もされている。しかし、根岸准教授は、まだ改善点が残されていると話す。
「現状の表面増強ラマン散乱素子は、凹凸を持つように成型した金属基板に偶然できたナノギャップへ試料を吸着させて分析を行います。しかし、混ざりもののある試料を分析する場合、標的となる分子のすぐそばに標的でない分子が付着している場合もある。すると、ラマン散乱光を得るのに使うレーザーのスポット径は1μm程度と大きいため、標的分子のシグナルも非標的分子のシグナルも同時に検出してしまうのです。そのため、背景ノイズが出てクリアな結果が得られなくなります。そこで、研究室では、これまでに蓄積してきた超微細加工法の知見を応用して意図的にナノギャップ構造を作り出し、単一分子レベルでシグナルを検出できる新たな表面増強ラマン散乱素子を開発することを目指しています」
根岸准教授は過去の研究で半導体の製造などに使われるリソグラフィーという技術を用いて金属を加工し、狙い通りのサイズでナノギャップ構造を作ることに成功している。その技術を応用して、単一の分子を選択的に分析することが可能な極小の電極を作ることができれば、より精度の高い表面増強ラマン散乱素子の開発に結び付くと考えたのだ。
「さらに、電極の両サイドに電熱線を配置して熱を加え、金属の熱膨張を利用することでナノギャップの幅を微調整する手法も検討しています。1nmがほんの0.3nmほど縮まるだけでラマン散乱の増強効果は非常に強くなります。このような工夫により、これまでにない超高感度の表面増強ラマン散乱素子を創り出そうとしています。ナノギャップは非常に特殊な構造であり、難しい研究分野です。しかし、うまく利用することで、今まで見えなかったものが見えてくるという面白さがあります」

医療分野への応用も視野に
超高感度の表面増強ラマン散乱素子が実現すると、分子の構造をより高い精度で、しかもスピーディーに解析することができるようになると考えられる。そうすれば、病気の原因となる生体物質や、がんの進行とともに増える、腫瘍マーカーと呼ばれる物質を素早く検出し、病気の早期発見・治療が可能になる。
「コロナ禍のようなパンデミックが起きた場合にも有用な技術だと考えています。感染しているか否かをスピーディーに判定できれば、その後の対応が大きく違ってきますから。現在は、産学連携の研究により、超高感度表面増強ラマン散乱素子の大量生産を可能にする自動作成装置の開発をスタートしており、一刻も早い実用化を目指しています」
根岸准教授は炭素原子で六角形の格子構造を形成したシート状の物質、グラフェンの研究に取り組んでいたことがある。物理学の新たな分野を切り拓くとされているグラフェンだが、研究が進み、電磁波を照射すると前述の表面プラズモンと同様の現象が起きることがわかってきた。しかも、金属の板に照射した時とは全く異なるテラヘルツ帯という振動周波数を発生させるのだという。
「テラヘルツ帯は、これまで発生させることも検出することも困難であった未踏の周波数帯でした。しかし、グラフェンを用いることでテラヘルツ帯を実用に結びつけることが可能になるかもしれません。将来、テラヘルツ帯で機能する表面増強ラマン素子を開発することができれば、分子の構造解析も新たなステージに進むのではないかと期待しています」
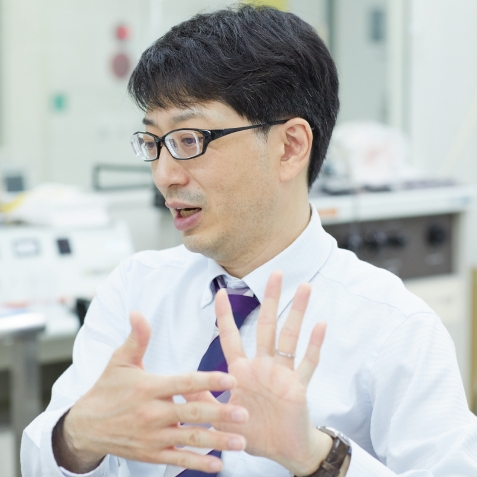 取材日(2021年6月)
取材日(2021年6月)
所属・身分等は取材時点の情報です。
MORE INFO. 関連情報