Q.教員としてご自身の専門分野を踏まえ、「研究者として研究」することの意味とは?
社会に貢献する
社会に育てられ、社会の恩恵により豊かな生活を送ることができます。研究により新たな技術、手法、考え方などを開拓し、いろいろなかたちで社会や学問に貢献することができると思います。自身の人生も創造的で豊かなものにできると思います。
Q.教員としてご自身が、研究者になった経緯をご紹介ください。
いろいろな世界を科学で探求する
子供の頃は成長目覚ましい日本でしたが、その頃すでに環境問題や資源問題が大きく取り上げられていました。将来に備えてどんな学問や実力を身につけたら良いだろうと思いながら、化学に立脚する資源・環境分野に進もうと思いました。実際、生命、自然、暮らしや健康に関わる物質など、どれもが化学で成り立ち動いていると言って過言じゃないからです。大学院で基礎研究の魅力と力を知り、当時の恩師の勧めもあって大学で研究する道を選びました。当時は売り手市場で日本企業も活気があり、基礎研究で生きる道をどうかなと思ったこともありましたが愉快な研究生活です。
Q.教員としてご自身のご専門分野について、現在までにどんなテーマを研究されているのかご紹介ください。
エネルギー・環境技術から環境学、経済学との出会い
学部、大学院では水素エネルギーに関する研究に取り組みました。これを契機として環境材料と環境保全に関わる工学技術の開発に取り組みました。一方で、国に提案したテーマが採択され、高レベル放射性廃棄物の処分研究のプロジェクトに長らく関わることができました。経産省所管の研究所や原子力研究開発機構における処分研究の大型プロジェクトに関わる実務経験はとても有意義なものでした。東洋大学ではグリーンプロセス研究(主に水に関連するテーマ)を行う一方で、環境関連の学識や実務経験をいかして環境学や環境経済学(環境問題に関わる統計分析)に関するテーマに関心を持って活動をしています。
Q.研究者として、つらかったことや、嬉しかったことは?
自分を変える
学生時代の研究を通じてテーマ設定やアプローチの大切さを痛感しました。若かった私にはとても重要な学びでした。いつも研究の魅力やオリジナリティにこだわり彷徨い鼓舞しています。学会に参加し色々な研究にふれること、新たな開発や発見、論文採択、研究提案の採択、いずれも活力が湧き研究者(この言葉は意識していない)は愉快だなと感じています。多くの研究者と出会えたことも「研究を続ける」ということを牽引しました。
Q.大学院で学ぶことの魅力とは?
新しい世界と出会い、自分の力を伸ばし、自分のアイデアを創造する
魅力を意識することはないですが、そこに可能性や未来があると感じることかもしれない。
Q.大学院で学びを考えている受験生にメッセージを一言。
新しい事をやる開拓者になろう
生き抜く力を備えるつもりでチャレンジしては如何でしょうか。
プロフィール
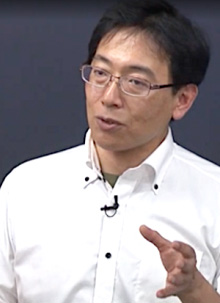
氏名:清田 佳美(せいだ よしみ)
経歴:現在、東洋大学大学院経済学研究科経済学専攻 教授
大学と原子力関連の研究所で開発研究を行う。公益法人やシンクタンクで実務経験を積む。
2011年に本学に着任。本学ではこれまでの実務経験に基づき、環境学や環境経済学を講義する。
ライフワークに「水の自然誌」や「ゲル体」に関わる研究・教育がある。
専門:工学技術、環境学、環境経済学
掲載されている内容は2022年7月現在のものです
MORE INFO. 関連情報
