
FACULTY OF INFORMATION SCIENCES AND ARTS 総合情報学部 総合情報学科 川越キャンパス
About
文理を超えた学問分野の広さと多様性、
「情報」を軸に専門性を深化させる
文理融合のカリキュラムにより、文系・理系の枠にとらわれない総合的な知識とスキルを培い、自らの志向と興味関心に合わせた学びを深めます。「メディア情報専攻」「心理・スポーツ情報専攻」「システム情報専攻」の3つの専攻で、特徴豊かな学びを展開。AIやデータサイエンスの専門的なスキルの習得も可能です。実践的な学びを組み合わせながら、ウェルビーイングの実現に向けたアプローチを身につけていきます。各教員が一人ひとりに丁寧に寄り添い、授業はもちろん、大学環境への適応、資格取得や卒業後の進路などについても、サポートが充実しています。
総合情報学科の3つの特徴
01 ITを駆使して心理・スポーツにアプローチ

心理・スポーツ情報専攻では、心理学の理論と実践に加え、ITを駆使したアプローチも学べます。NSCA認定パーソナルトレーナーの資格取得を目指せます。
02 機械学習・統計解析を通して社会課題に挑戦

システム情報専攻では、AIやネットワーク技術などを中心に学びます。社会調査士や高校「情報」教員免許も取得可能です。
03 メディアコンテンツ制作の知識と技能を修得

メディア情報専攻では、3DCGコンテンツ制作とVR表示、ユーザの操作に応じて即座に応答するシステム構築の能力などを養う教育を展開しています。
# こんなことも総合情報学科の学び
文理融合を特徴とする総合情報学科の学びにはさまざまな可能性があります。例えば、スポーツと心理学が融合した分野を学ぶことで、スポーツメンタルトレーニング指導士を目指せます。スポーツとITの融合では、多彩な種目のスポーツデータアナリストを目指すことが可能です。また、AIとメディアでは、メディアの各分野におけるAI技術の応用で、AIアプリやAIを用いたゲームの開発等も学べます。
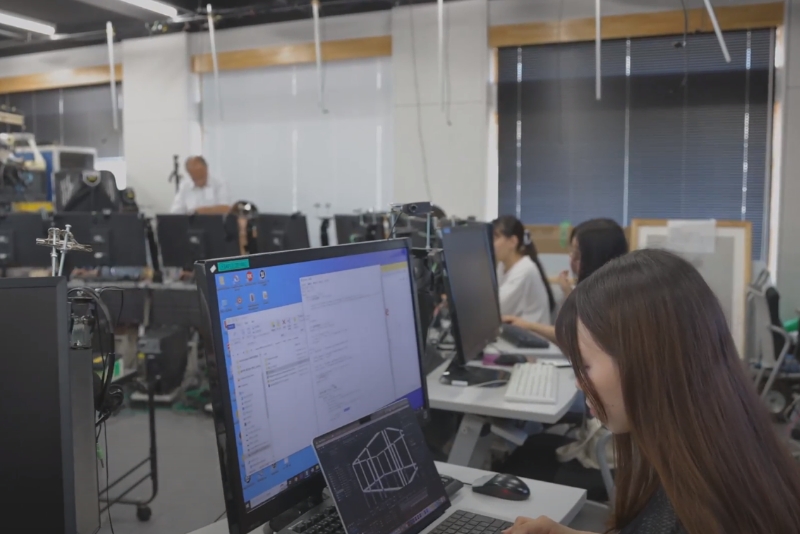
教員一覧
こんな資格がめざせます
メディア情報専攻
- 情報処理技術者
- マルチメディア検定
- CGクリエイター検定
- CGエンジニア検定
- Webデザイナー検定
- ウェブデザイン技能検定
- 画像処理エンジニア検定
- CAD利用技術者試験
心理・スポーツ情報専攻
- 社会調査士
- 認定心理士
- 情報処理技術者
- NSCA CSCS (Certified Strength and Conditioning Specialist)
- NSCA-CPT (NSCA Certified Personal Trainer)
システム情報専攻
- 高等学校教諭一種(情報)
- 社会調査士
- 情報処理技術者
- 技術士
- 日商簿記1~3級
- ファイナンシャル・プランナー
※上記資格の一部は、卒業・単位修得以外に条件があるものを含みます。詳細は 取得可能資格一覧(PDF: 1ページ)をご確認ください。
教育の目的・3つのポリシー
メディア情報専攻
- 教育研究上の目的
-
1.人材の養成に関する目的
メディア情報専攻では、様々な目的や対象に応じて適切なメディアを選択し、コンピュータを使用して魅力的なコンテツを制作し発信することで、人々の心を豊かにするコンテンツを制作できる人材を養成する。また、AI技術を使用して多様なコンテンツを生成できるシステムを構築することで、コンテンツの作り手を手助けし、コンテンツの受け手の心を豊かにすることができる人材の育成を教育研究上の目的とする。
2.学生に修得させるべき能力等の教育目標
1)CGサイエンス分野
3次元コンピュータグラフィックスを使用したコンテンツを制作し、それを仮想現実空間に表示し、ユーザの操作に応じてリアルタイムに応答を返すシステムを構築できる能力を養うための教育を行う。
2)AIシミュレーション分野
深層ニューラルネットワークを使用して、イラストや楽曲や映像といった多様なコンテンツを制作することができる生成系AIシステムを構築できる能力を養うための教育を行う。
3)表現科学分野
グラフィックデザインが果たす役割を理解し、実際にコンピュータを使用して視覚的なコンテンツを制作し、それをWebページ・アプリ等を通して発信することができる能力を養うための実践的な教育を行う。
4)メディア文化分野
文化を創造する営みの本質を捉えるとともに、現代社会におけるメディアの多様な役割と影響力を理解し、心豊かな生活の礎となる文化を創造する能力を養うための教育を行う。
3.その他の教育研究上の目的
メディア情報専攻では、メディアの多様な役割や影響力を理解するための教育を行い、同時により良いコンテンツを作成する方法を身につける教育を行う。その上で、最新のCG・VR技術を使用したシステムの構築方法や、AI技術を使用した多様なコンテンツの自動生成手法を学ぶことで、人々の心を豊かにするシステムやコンテンツを作成できる人材を育成する。 - ディプロマ・ポリシー
-
メディア情報専攻では、文理融合のもと、CG・VR、生成系AI、シミュレーション、グラフィック・Webデザイン等の情報通信技術を駆使し、メディアコンテンツによって「心豊かな生活」を実現することで、ウェルビーイングに貢献できる人材を育成するという教育目標のもとに、次の基準を満たす学生に卒業を認定し、学位を授与する。
1)知識・技能:メディアの役割やより良いコンテンツを作成する方法に関する知識を有し、コンピュータを用いて多様な形式のコンテンツを作成する技能を有する。
2)思考力・判断力、表現力等の能力:多様な事象に応じて適切な表現手段を選択し、様々なツールを使用して実際に表現できる能力を有する。
3)主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度:多様なコンテンツ制作の演習や卒業研究を通して、他者とコミュケーションをとりながら主体的に行動できる能力を有する。 - カリキュラム・ポリシー
-
メディア情報専攻では、「心豊かな生活」の実現の上で求められる高度な知識力、判断力、技術力を養うという教育目標およびディプロマ・ポリシーに求める学修成果の修得を実現するため、以下の方針でカリキュラム(教育課程)を編成する。
1. 情報デザイン学、感性情報学、知能情報学などの学問分野を主軸に置き、専門性を高めるよう「メディア文化」「表現科学」「CGサイエンス」「AIシミュレーション」の4つの分野を編成し、基盤教育の履修により、「自然科学」「人文科学」に関連する幅広い知識を修得することができるよう編成する。
2. より良いコンテンツを作るための「知識」や「技能」を養うため、「メディア文化」「表現科学」分野の専門科目を基礎から応用まで配置し、順に履修することで段階的に学習できるようにする。
3. 適切な表現手段を選択するための「思考力」「判断力」、実際に表現するための「表現力」を養うため、「CGサイエンス」「AIシミュレーション」分野の専門科目を基礎から応用まで配置し、順に履修することで段階的に学習できるようにする。
4. 主体性を持ち、多様な人々と協働して学ぶ態度を身につけるため、1年秋学期より4年秋学期まで通して演習科目を配置する。
5.自らの問題意識で物事を解明する力を身につけるために、「卒業論文」を必修にする。 - アドミッション・ポリシー
-
メディア情報専攻では、本専攻の卒業の認定及び学位授与に関する方針に基づいて編成された教育を受けることができる者として、文系・理系を問わず、以下に記した知識・技能、思考力・判断力等の能力、態度を持つ者を受け入れる。
(1)メディアコンテンツを活用した「心豊かな生活」の実現を通じて、ウェルビーイングに貢献する意思のある者。
(2)コンピュータを用いて様々な形式のコンテンツを作成する技術を身につける意欲のある者。
(3)メディアの多様な役割と影響力を理解した上で、より良いコンテンツを作成する方法を学ぶ意欲のある者。
(4)多様なコンテンツを容易に制作できる人工知能技術に関心をもつ者。
(5)大学での修学に必要な基礎学力を有する者。具体的には、国語、英語、数学および文系であれば社会、理系であれば理科の基礎学力を有する者。
入学試験においては、多様性を重んじ、筆記試験だけでなく、面接を中心とした選抜方式も採用し、本専攻で学びたい意欲のある学生を、文系・理系、また国内外問わず、広く募集する。
心理・スポーツ情報専攻
- 教育研究上の目的
-
1.人材の養成に関する目的
心理・スポーツ情報専攻では、心理学を「心」、スポーツを「体」、ICTを「技(術)」と捉え、この3つを学ぶことで「心・技・体」の充実を図り、これにより学生の「心豊かな生活」「心身の健やかさ」を目指す。また、これらを単に知識として備えるのみでなく、各セメスターに配置される演習科目により、それらの知識を実践に用いることで、「安全・安心・快適な社会」作りにも貢献できる技術を同時に身に付けることを教育研究上の目的とする。
2.学生に修得させるべき能力等の教育目標
1)心理情報分野
心理を中心にカウンセリングや心理実験に加えて、ITカウンセリング・メンタルトレーニングなど、ITを駆使し、心理とITの融合領域を先導できる能力を養うための教育を行う。
2)スポーツと心理学分野
パーソナルトレーナーや認定心理士等に求められる心身の仕組みに関する知識を身につけ、これらの資格の取得が可能になる能力を養うための教育を行う。
3)スポーツ情報分野
シミュレーションやAIなどのITを用いて、運動する身体やゲーム中のプレイヤーの動きを測定・解析し、科学的に理解・説明する能力を養うための教育を行う。
4)データサイエンス分野
社会調査データ、心理・身体データに対して機械学習・統計解析を行うことで、ヒトの心理や行動を解析し、科学的に説明できる能力を養うための教育を行う。
3.その他の教育研究上の目的
心理・スポーツ情報専攻では、心理学やスポーツを専門としてしっかり学んだ上で、これらの知識をICTによって広く社会に活用できるデジタル人材の育成を行う。実習については、心理関係の施設を訪問し、心理的援助の実際を学ぶ。さらに社会調査関係の実習においては、実際のフィールドでの調査を行う。また、資格の取得を目指す学生や部活動に注力する学生などは学外に出る機会が多い。そこでオンデマンドの科目を多く準備し、終日学外活動できる曜日を設けることで、学生の自由な活動を支援しつつ十分な教育ができるようにする。 - ディプロマ・ポリシー
-
心理・スポーツ情報専攻では、文理融合により心理およびスポーツの分野でAI、データサイエンス等の情報通信技術を駆使し、「心身の健やかさ」を実現することで、ウェルビーイングに貢献できる人材を育成するという教育目標のもとに、次の基準を満たす学生に卒業を認定し、学位を授与する。
1)知識・技能:心理情報分野では、「臨床心理学」、「産業・組織心理学」、「心理学統計法」、スポーツ情報分野では「運動科学」、「スポーツメカニクス」、「スポーツ情報処理」、スポーツと心理学分野では「スポーツ行動心理学」、「トレーニングにおけるリスクマネジメント」、「エクササイズ指導」などの知識を有する。
2)思考力・判断力、表現力等の能力:上記の知識にITを利活用することで社会に役立つ実践力を有する。
3)主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度:スポーツおよび心理学を題材とした演習や卒業研究を通して、社会の多様性に関する理解と、相手の立場・考え方を尊重しつつ主体的に行動する力を身につけている。 - カリキュラム・ポリシー
-
心理・スポーツ情報専攻では、「心身の健やかさ」の実現の上で求められる高度な知識力、判断力、技術力を養うという教育目標およびディプロマ・ポリシーに求める学修成果の修得を実現するため、以下の方針でカリキュラム(教育課程)を編成する。
1. 心理学、スポーツ科学、情報学などの学問分野を主軸に置き、専門性を高めるよう「心理情報」「スポーツと心理学」「スポーツ情報」「データサイエンス」の4つの分野を編成し、基盤教育の履修により、「自然科学」「人文科学」に関連する幅広い知識を修得することができるよう編成する。
2. 1〜3年次それぞれに上記4分野の専門科目を基礎から応用まで配置し、順に履修することで段階的に学習ができるようにする。
3. 「思考力」「判断力」「表現力」を養うため、1年次からそれぞれの段階に応じて実践的な科目を配置する。
4. 主体性を持ち、多様な人々と協働して学ぶ態度を身につけるため、1年秋学期より4年秋学期まで通して演習科目を配置するとともに、卒業論文を必修とする。
5. 各種資格に必要な科目を無理なく取得できるよう1〜3年次にバランスよく配置する。 - アドミッション・ポリシー
-
心理・スポーツ情報専攻では、本専攻の卒業の認定及び学位授与に関する方針に基づいて編成された教育を受けることができる者として、文系・理系を問わず、以下に記した知識・技能、思考力・判断力等の能力、態度を持つ者を受け入れる。
(1)「心身の健やかさ」の実現を通じて、ウェルビーイングに貢献したいという意思を有する者。
(2)人の心に興味があり、心理学を社会に役立てたいという希望を有する者。
(3)自身がスポーツを実践し、または観戦するなどスポーツ分野に対する興味を有する者。
(4)IT(情報通信技術、人工知能、ビッグデータなど)をスポーツまたは心理分野に応用することに可能性を感じる者。
(5)大学での修学に必要な基礎学力を有する者。具体的には、国語、英語、数学および文系であれば社会、理系であれば理科の基礎学力を有する者。
入学試験においては、多様性を重んじ、筆記試験だけでなく、面接を中心とした選抜方式も採用し、本専攻で学びたい意欲のある学生を、文系・理系、また国内外問わず、広く募集する。 - 教育研究上の目的
-
1.人材の養成に関する目的
システム情報専攻では、プログラミングスキルならびに情報学分野の知識をもとに、AI、システム・ソフトウェア、データサイエンス等の情報通信技術を駆使したDX(デジタルトランスフォーメーション)によって「安全・安心・快適な社会」の実現を以てウェルビーイングに貢献できる人材を育成するための教育を行うことを教育研究上の目的とする。
2.学生に修得させるべき能力等の教育目標
1)AI応用領域
AIの仕組みを理解し、高度なAI技術を駆使した自動化、省人化によって、安全・安心・快適な社会を実現する革新的な仕組みを創り出すためのの実践的な教育を行う。
2)システム・ソフトウェア開発領域
社会の高度なDX化により安全・安心・快適な社会の実現に資するシステム・ソフトウェアを開発するための教育を行う。
3)ビジネス創生領域
AI・IoT・ビックデータを活用し、安全・安心・快適な社会の実現を可能にするビジネスを創出できる能力を養う教育を行う。
4)プログラミング領域
上記3領域の教育研究に求められる高度なプログラミング技術を身につけるための教育を行う。
3.その他の教育研究上の目的
システム情報専攻では、数学・プログラミング教育の必修化・充実化すると同時に、情報学分野の学習を軸に据える。その上で、AI応用分野の高度な学びを提供し、AI、システム・ソフトウェア、データサイエンス等の情報通信技術を駆使したDX(デジタルトランスフォーメーション)によって「安全・安心・快適な社会」の実現を以てウェルビーイングに貢献できる高度な理系人材の育成を行う。 - ディプロマ・ポリシー
-
システム情報専攻では、プログラミングスキルならびに情報学分野の知識をもとに、AI、システム・ソフトウェア、データサイエンス等の情報通信技術を駆使したDX(デジタルトランスフォーメーション)によって「安全・安心・快適な社会」の実現を以てウェルビーイングに貢献できる人材を育成するという教育目標のもとに、次の基準を満たす学生に卒業を認定し、学位を授与する。
1)知識・技能:情報通信技術の知識を持ち、社会の問題解決に資するプログラミング、AI活用、システム・ソフトウェア開発、データ分析の技能を有している。
2)思考力・判断力、表現力等の能力:社会における問題を自ら定義し、AI、システム・ソフトウェア、データの活用によってその解決を図ることができる能力を有している。
3)主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度:システム・ソフトウェア開発、要件定義を題材とした演習や卒業研究を通して、社会問題ならびにその多様性に関する理解と、相手の立場・考え方を尊重しつつ主体的に行動する力を身につけている。 - カリキュラム・ポリシー
-
システム情報専攻では、「安全・安心・快適な社会」の実現の上で求められる高度な知識力、判断力、技術力を養うという教育目標およびディプロマ・ポリシーに求める学修成果の修得を実現するため、以下の方針でカリキュラム(教育課程)を編成する。
1. AI、システム・ソフトウェア、情報学などの学問分野を主軸に置き、専門性と応用力を高めるよう「AI応用」「システム・ソフトウェア開発」「プログラミング」「ビジネス創造」の 4つの専攻分野を編成する。また、基盤教育の履修により、「自然科学」「人文科学」に関連する幅広い知識を修得することができるよう編成する。
2. 情報通信技術の「知識」、社会の問題解決に資するAI活用、システム・ソフトウェア開発、プログラミング、データ分析の「技能」を習得できるようにするために、上記4分野の専門科目を基礎から応用まで配置し、順に履修することで段階的に学習ができるようにする。
3. 社会における問題を自ら定義し、情報通信技術の活用によってその解決を図るうえで求められる高度な「思考力」「判断力」「表現力」を養うため、「ビジネス創造」専攻分野を設定し、他の科目分野で培った知識・技能を「安全・安心・快適な社会」の実現に向けて実装展開するための実践的な科目を配置する。
4. 主体性を持ち、多様な人々と協働して学ぶ態度を身につけるため、1年秋学期より4年秋学期まで通して、システム・ソフトウェア開発、業務要件定義を題材とした演習科目を配置するとともに、卒業論文を必修とする。
5. 教員第一種免許(情報)の取得に必要となる科目を提供する。 - アドミッション・ポリシー
-
システム情報専攻では、本専攻の卒業の認定及び学位授与に関する方針に基づいて編成された教育を受けることができる者として、文系・理系を問わず、以下に記した知識・技能、思考力・判断力等の能力、態度を持つ者を受け入れる。
(1)「安全・安心・快適な社会」の実現を通じて、ウェルビーイングに貢献する意思を有する者。
(2)社会に存在する問題に対する意識を持ち、AI・IoT・ビックデータなどの情報通信技術の活用によってその解決を図ろうとする強い意志を有する者。
(3)システム・ソフトウェア開発、データ分析に必要となる論理的思考能力を持つ、あるいはその能力を高め意志を有する者。
(4)AI利用、システム・ソフトウェア開発、データ分析の技術を身につける意志を有する者。
(5)大学での修学に必要な基礎学力を有する者。具体的には、国語、英語、数学、理科および文系であれば数学、理系であれば数学・理科を得意とする者。
入学試験においては、多様性を重んじ、筆記試験だけでなく、面接を中心とした選抜方式も採用し、本専攻で学意欲のある学生を、国内外問わず、広く募集する。
システム情報専攻
