
FACULTY OF SOCIOLOGY 社会学部 社会学科 白山キャンパス
About
グローバルな視野を持ち、
社会や個人の前に立ちはだかる課題に挑む
社会学科では、社会学を中心に周辺分野の諸科目の学習・研究を行います。家族、地域、組織、環境などの歴史・構造・問題を理解したうえで、グローバルな視野を持ちながら、現代社会において個人と社会が直面している多様な諸課題を理論と実証の両面から把握し、その課題の解決に挑みます。また、1年次から演習科目を開講し、最新の研究成果に直接触れながら積極的に学ぶ機会を提供しています。広範な研究対象を持つ社会学の特色を生かし、幅広い分野の学びの後に自らの研究対象を絞り込み、卒業論文に取り組むことになります。積極的に社会にコミットしたい方にとって、最適な学科と言えるでしょう。
社会学科の3つの特徴
01 社会の仕組みを理論的に捉える思考力を培う

社会学の諸学説を理解し、現代社会のメカニズムを理論的に捉える視座を身に着けます。
02 社会の現状を調査・分析する能力を獲得する

必修の社会調査関連科目を通じ高度な調査分析能力を獲得し、習得した方法論を実習科目等で実践します。
03 現代社会に対する深い理解と洞察力を育む

多様な分野にわたる社会現象に対する理解を深め、現代社会を領域横断的に捉える力を身に着けます。
# こんなことも社会学科の学び
【実行力と発信力を養う】:1年次〜4年次まで専任教員が担当するゼミに所属し、必修の卒業論文・卒業研究を完成させます。現代社会の中で主体的に行動し、他者との協働を通じて社会に貢献できる能力を養っていきます。
【グローバルな教養】:語学を含む基盤教育科目を通じて、グローバル化した現代社会を生きるために必要な幅広い教養が身に着く機会を提供しています。
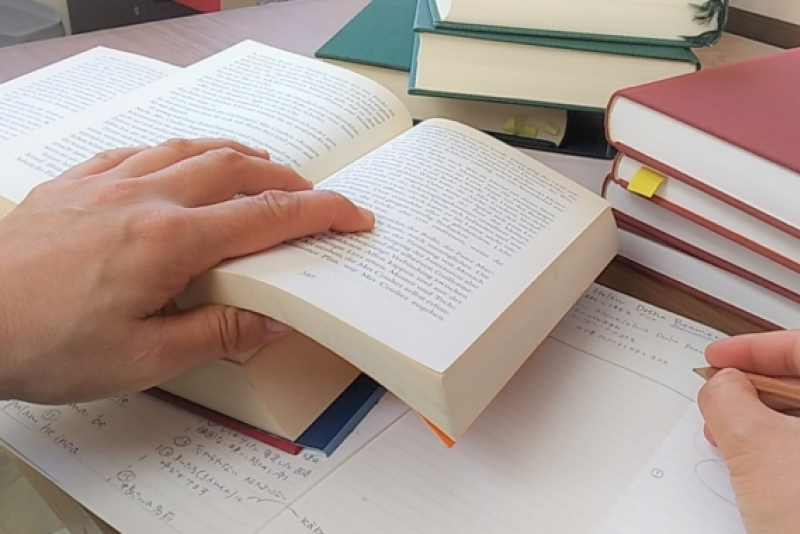
教員一覧
こんな資格がめざせます
- 中学校教諭一種(社会)
- 高等学校教諭一種(地理歴史・公民)
- 学芸員
- 社会調査士
- 社会福祉主事(任用資格)
※上記資格の一部は、卒業・単位修得以外に条件があるものを含みます。詳細は 取得可能資格一覧(PDF: 1ページ)をご確認ください。
教育の目的・3つのポリシー
- 教育研究上の目的
-
1.人材の養成に関する目的
社会学科の人材の養成に関する目的は、以下のとおりである。
(1)グローバル化により複雑化した現代社会を生きる個々人の境遇をより大きな歴史的・社会的な背景と関連づけて理解することのできる人材の養成
(2)「当たり前」にとらわれず社会現象や社会問題に関して、自分で考え、自分の言葉で意見を表明できる人材の養成を目的とする。2.学生に修得させるべき能力等の教育目標
社会学科の人材の養成に関する目的達成には、自学自習的・共同討論的学習スタイルを身につける必要がある。そのために、社会学科の学生に修得させるべき能力等の教育目標を以下のように設定する。
(1)社会学の基礎概念や考え方の修得
(2)社会学の歴史と意味の修得
(3)実証的研究方法(フィールドワークを含む)の修得
(4)現代社会や世界の複雑な側面の理解と問題解決力の修得
(5)演習による調査・発表・討論方法の修得
(6)問題意識の明確化と論文の基本要件の修得
(7)卒業論文(卒業研究)作成 - ディプロマ・ポリシー
-
社会学科では人材の養成に関する目的、学生に修得させるべき能力等の教育目標を鑑み、以下の能力、知識等を修得した学生に学位を授与する。
(1)多様な社会的・文化的背景をもった他者と協働して現代社会の諸問題の解決に貢献するための主体的な実行力とグローバルな発信力
(2)現代社会のメカニズムを捉えるための理論的思考力
(3)現代社会の中から課題を発見し、それを意味的、計量的、空間的に精確に捉える社会調査能力
(4)現代社会が直面している諸問題に対する理解およびそれらを横断的に捉える洞察力
(5)グローバル化した現代社会で自らの力でキャリアを研鑽していく市⺠にふさわしい哲学を中⼼とした幅広い教養 - カリキュラム・ポリシー
-
社会学科の教育目標達成のため、以下の方針により教育課程を編成する。
(1)幅広い分野の科目を配置する全学基盤教育科目および全学共通教育科目と語学科目、学科専門科目および学部共通科目からなる専門教育科目に大別した構成とする
(2)全学基盤教育科目では東洋大学の理念を学ぶため哲学・自校教育科目から2単位を必修とするほか、全学的な教育目標を定めた科目を配置する。全学共通教育科目では総合大学の強みを生かし幅広い分野の科目を配置する
(3)学部共通科目では幅広い社会学分野の科目を配置する。1年次に社会学の全体像を学び、同時に社会学科で重点を置いている社会調査の基礎を学ぶ。語学科目ではグローバル化に対応するため複数の語学科目を配置する
(4)学科専門科目では1年次から4年次まで少人数制のゼミナールを必修とするほか、集大成として4年次に卒業論文が執筆出来る知識、能力を身に着けるため、現代社会の多種多様な現象を理解し、複雑化している現代社会を領域横断的に学べるよう、社会学はもとより社会学の隣接領域科目を配置する
(5)社会学科で修得可能な社会調査士、教育職員免許状(中学・社会、高等学校・地理歴史、公民)に即した科目を配置する - アドミッション・ポリシー
-
社会学科では、グローバル化した現代社会を生きる個々人の境遇をより大きな歴史的・社会的な背景と関連づけて理解することのできる市民となるポテンシャルをもつ次のような人材を求めています。
(1)自分とは異なる意見を尊重し、他者との活発な意見交換を通じて自分自身の考えをさらに深める姿勢をもち、また自分自身の考えを発信することができる人
(2)現代社会について書かれた文章を精確に読み、理解できる言語能力をもつ人
(3)教室で学んだことや他者から聞いたことに関心をもち、自分自身でさらに深く調べることのできる積極性をもつ人
(4)さまざまな社会現象や社会問題を理解するための前提となる地理、歴史、現代社会に関する基本的な知識をもつ人
(5)哲学を中心とした幅広い教養を身につけるための土台となる語学力を含めた基礎学力をもつ人
