
INTERVIEWEE
矢野 了平
YANO Ryouhei
2001年 東洋大学 文学部第2部教育学科[現・教育学科(イブニングコース)] 卒業
構成作家・クイズ作家
1977年埼玉県生まれ。東洋大学在学中、クイズサークル「SQUEEZE」に所属。『全国高等学校クイズ選手権(日本テレビ系)』のアルバイトがきっかけで、大学卒業後、構成作家事務所「CAMEYO」に所属。『トリビアの泉~素晴らしきムダ知識~(フジテレビ系)』『水曜日のダウンタウン(TBS系)』『佐藤健&千鳥ノブよ!この謎を解いてみろ!(TBS系)』『今夜はナゾトレ(フジテレビ系)』など多数のテレビ番組で構成作家として活躍中。
幼少期から没頭したクイズ。好きが高じて、仕事になるまでの道のり

――矢野さんがクイズを好きになったきっかけは何だったのでしょうか?
やはり、テレビのクイズ番組がきっかけだったと思います。小学校の頃からクイズ番組をよく見ていましたし、本屋でクイズの本を買っては友人と出し合って楽しんでいました。誰しも一度は感じたことがあると思いますが、家族や友人の中で自分だけが正解できた時の優越感は、何とも言えない快感ですよね。そうした「知的優越感」に魅了され、気がつけばクイズにのめりこんでいました。高校ではクイズ研究会に所属し、放課後は東京の大学生を中心としたクイズサークルにも参加。東洋大学でもクイズサークル「SQUEEZE」に入り、朝霞キャンパスや先輩の自宅に集まっては、それぞれが持ち寄った問題を解いていました。夏休みや冬休みには合宿を開催し、バラエティ番組を模した企画で盛り上がることもありましたね。
――大学時代に、クイズ番組の作問アルバイトをされていたと伺いました。
高校時代にお邪魔していたサークルの先輩の紹介で、『全国高等学校クイズ選手権(日本テレビ系)』のアルバイトをしていました。最初は受付や参加生徒の誘導などを担当していましたが、3年生になる頃には作問も任せてもらえるように。専用の用紙に問題と答え、解説、出典などを記入し、1週間後に提出する。そんなルーティンを毎週繰り返すうちに、面白いクイズを作るための発想力が鍛えられました。当時はクイズが仕事になるとは思っていなかったのですが、ある日突然、番組のプロデューサーから「構成作家になれ」と言われたのです。構成作家とは、番組全体の構成を考えたり、クイズの企画を取りまとめたりする仕事です。一度挑戦してみようと思った私は、思い切って構成作家事務所に所属しました。大学卒業までの間は、アルバイトとしてクイズの正確性を検証するリサーチにも携わりました。実は、テレビで放送されるクイズは、辞書や文献によるチェックに加え、専門家への電話取材という二重の検証を経ています。自分の作ったクイズがどのようなプロセスを経て世に出ているのかが分かると同時に、クイズ番組の制作に本格的に携わっているという実感が湧き、とてもワクワクしたことを覚えています。
クイズや謎解きが流行している理由とは?その魅力を聞いてみた

――クイズづくりの醍醐味を教えてください。
クイズを作る際には、「どうすれば楽しくなるか」「どうすれば面白いと思ってもらえるか」という視点を常に意識しています。自由な発想をふくらませ、そこに少しひねりを加えて考えることが、クイズづくりの醍醐味です。
また、構成作家としては「身近にあるけれど誰も気付いていないところに目を付けて、面白く使えたとき」が醍醐味ですね。これを実現できた例が、『クイズ☆タレント名鑑(TBS系)』の企画。遊園地の中に潜む「かつて活躍していた有名人」を探し出し、名前を言えたら確保できるという形式のクイズを考えました。これは、街中で見かけた人に対して「あの人、芸能人じゃない?でも名前何だっけ……」となるあの体験から連想したものです。結果として、芸能人の名前を当てるというシンプルなクイズに『逃走中(フジテレビ系)』のようなゲーム性を掛け合わせたことで、理想に近い面白い企画に仕上げることができたと思います。
他にも、『佐藤健&千鳥ノブよ!この謎を解いてみろ!(TBS系)』では、東京タワーの色を変えるというギミックを取り入れました。佐藤健さんの手元に、あらゆるライトの色を変えられるリモコンを用意し、それを使って東京タワーの色を変えることで、離れた場所にいるノブさんに時限爆弾を解除するコードの色を伝える、という仕組みです。リモコンに着目し、「東京タワーの色を自分の意志で変えられる」とひらめけるかどうかが鍵となり、視聴者も思わず驚く展開になりました。こうした「シンプルなのに誰も気付かなかった」発想を生み出せると、面白い企画ができます。そのヒントは、身近な生活の中に眠っていますよ。
――最近では、謎解きがブームになっています。人気の理由はどこにあるとお考えですか?
私は、「クイズ」と「謎解き」には本質的な違いがあると考えています。クイズは問題があり、それに正解するもの。謎解きはミッションがあり、それを達成するものです。近年、謎解きが人気を集めている理由は、単に問題を解くだけではなく、犯人を捕まえたり、時限爆弾を解除したり、沈む豪華客船から脱出したりといった、ストーリーの中でミッションをクリアするという体験が味わえるからではないでしょうか。謎解きの謎自体は、法則クイズでもクロスワードパズルでも構わず、重要なのはミッションをクリアできるかどうか。だからこそ、ワクワクするのだと思います。私自身、クイズには体験としての要素が少ないことに引っかかっていました。そこで、クイズで謎解きのような体験ができないかと考え、クイズを取り入れた脱出ゲームを作りました。魔物を倒しながら図書館を脱出するという世界観の中で、クイズを解くという企画です。謎解きブームのおかげで、クイズの可能性をさらに広げることができたと感じています。
日常生活はネタの宝庫!矢野さん流面白いクイズの作り方
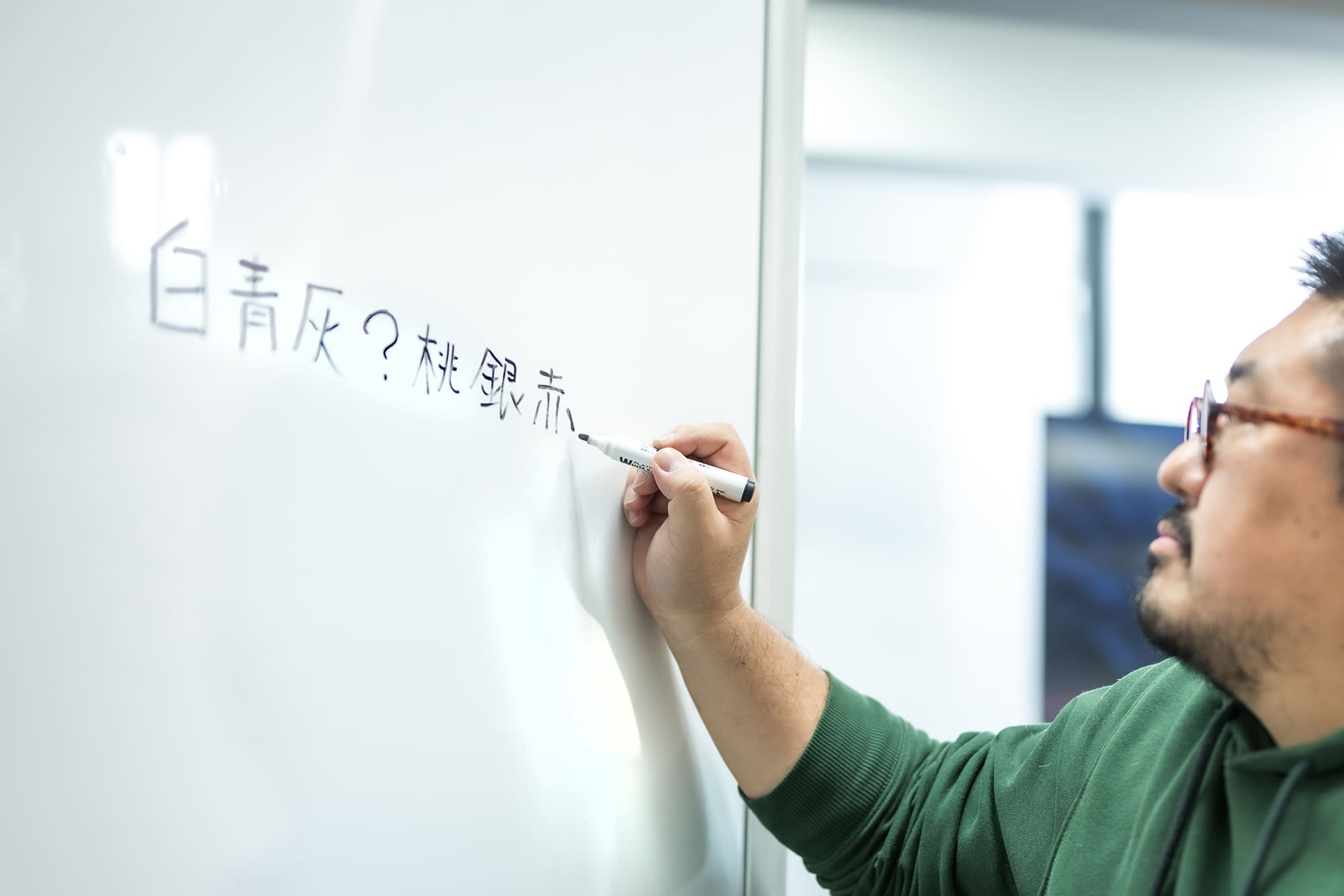
――初心者も参考にできる、クイズの作り方のポイントを教えてください。
クイズづくりにはさまざまなコツがありますが、初心者でも実践しやすいポイントを3つご紹介します。
① 選択式クイズをつくるコツは、“いいウソ”をつくこと。
初心者が最も作りやすいのは、選択式クイズでしょう。例えば、会社のクイズ大会で「上司の意外な趣味」を出題するとしましょう。不正解の選択肢を考える際には、「上司がこれをやっていたら面白いかも」という“いいウソ”を考えることがポイントです。思わず信じてしまいそうな、なおかつ笑える選択肢を作ることで、クイズのクオリティがぐっと上がります。
② 耳で聞いたときのわかりやすさを意識して。
クイズは内容だけでなく、言葉選びも重要な要素です。テレビではテロップが表示されますが、実際、回答者たちは問題を耳で聞いて答えます。例えば「夏季五輪」よりも「夏のオリンピック」の方が耳で聞いてすぐに理解しやすいですよね。音読みを多用する「熟語」をなるべく避けて、わかりやすい表現にするよう心掛けましょう。
③ 出題するシーンによって“良いクイズ”は異なる。
「良いクイズ」の基準は出題する場面によっても異なります。競技クイズの早押し問題では、問題文を読み進めるにつれて徐々にわかりやすいヒントが出てくるのがセオリー。一方で、バラエティ番組では少しひっかかりのある切り出しの方が面白かったりします。例えば、「本名をスガラグチャー・ビャンバスレンといい、叔父に朝青龍を持つ、今年横綱に昇進した人は誰?」という問題文は、競技クイズであれば情報の積み重ねがあり良い問題ですが、バラエティとしては、最初の情報が難しすぎて視聴者や回答者が置いてけぼりになる可能性があります。バラエティで出すなら、「叔父が朝青龍で」という情報を最初に持ってきた方が、エンタメとしてわかりやすく、回答者のリアクションも引き出せる良いクイズになると思いますね。
――矢野さんがクイズを作る時に参考にしているものはありますか?
普段から、SNSやラジオ、日常の中で面白いと感じたことや気付きを書き留めています。例えば、災害時の備蓄方法として知られる「ローリングストック」。この言葉を聞いた時、まるでプロレス技のようだと感じました。その時のメモを見返して、「この言葉、時事ニュースワード?それともプロレス技?」というクイズを考えたことがあります。また、電車でコンタクトレンズの洗浄液の広告を見た際に、「洗浄液」のすべての漢字に“さんずい”がついていることに気付きました。「他にも同じ部首が3つ並ぶ熟語はあるのだろうか?いつか活用できるかもしれない」と思い、メモしました。こうした日常生活でのストックが、クイズのアイデアにつながっています。特別な情報源ではなく、普段の生活の中にクイズのアイデアはたくさん転がっているんです。
