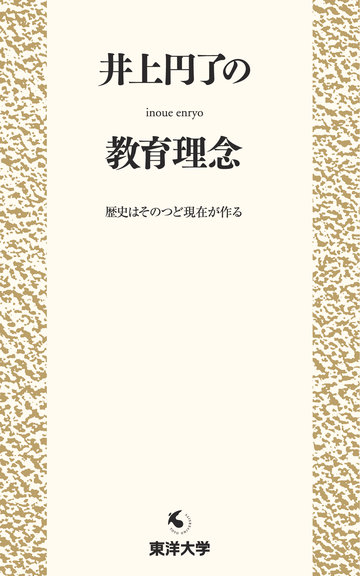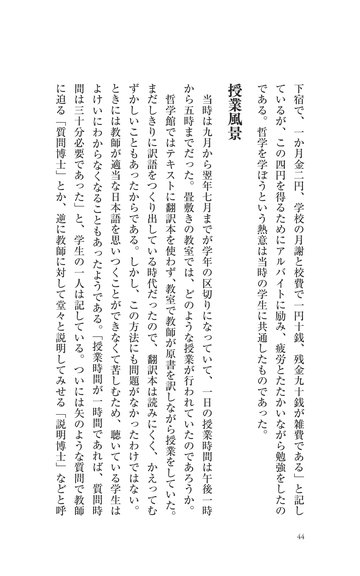井上円了の教育理念
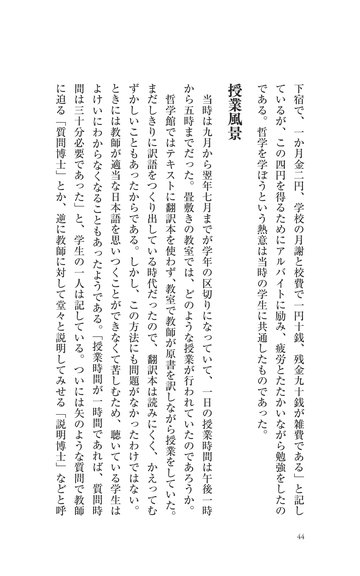
- ページ: 48
- 下宿で、一か月金二円、学校の月謝と校費で一円十銭、残金九十銭が雑費である」と記し
ているが、この四円を得るためにアルバイトに励み、疲労とたたかいながら勉強をしたの
である。哲学を学ぼうという熱意は当時の学生に共通したものであった。
授業風景
当時は九月から翌年七月までが学年の区切りになっていて、一日の授業時間は午後一時
から五時までだった。畳敷きの教室では、どのような授業が行われていたのであろうか。
哲学館ではテキストに翻訳本を使わず、 教室で教師が原書を訳しながら授業をしていた。
まだしきりに訳語をつくり出している時代だったので、翻訳本は読みにくく、かえってむ
ずかしいこともあったからである。しかし、この方法にも問題がなかったわけではない。
ときには教師が適当な日本語を思いつくことができなくて苦しむため、聴いている学生は
よけいにわからなくなることもあったようである。 「授業時間が一時間であれば、質問時
間は三十分必要であった」と、学生の一人は記している。ついには矢のような質問で教師
に迫る「質問博士」とか、逆に教師に対して堂々と説明してみせる「説明博士」などと呼
44
�
- ▲TOP