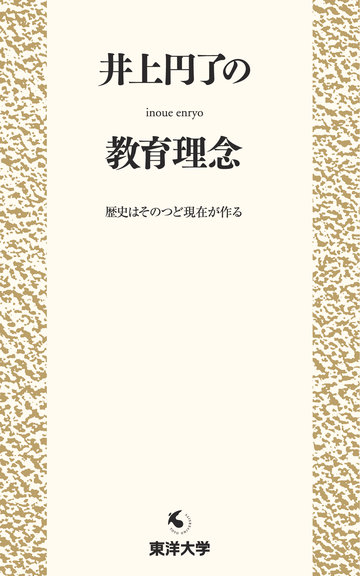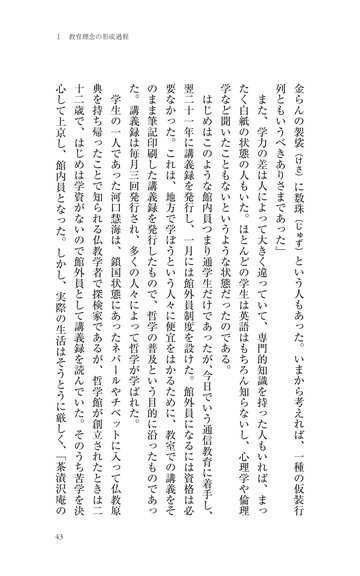井上円了の教育理念
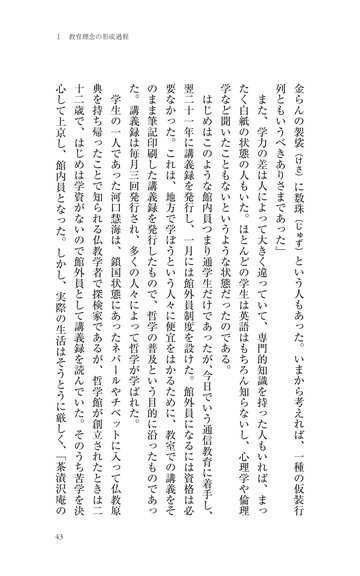
- ページ: 47
- 金らんの袈裟(けさ)に数珠(じゅず)という人もあった。いまから考えれば、一種の仮装行 列ともいうべきありさまであった」
また、学力の差は人によって大きく違っていて、専門的知識を持った人もいれば、まっ
たく白紙の状態の人もいた。ほとんどの学生は英語はもちろん知らないし、心理学や倫理
学など聞いたこともないというような状態だったのである。
はじめはこのような館内員つまり通学生だけであったが、 今日でいう通信教育に着手し、
翌二十一年に講義録を発行し、一月には館外員制度を設けた。館外員になるには資格は必
要なかった。これは、地方で学ぼうという人々に便宜をはかるために、教室での講義をそ
のまま筆記印刷した講義録を発行したもので、哲学の普及という目的に沿ったものであっ
Ⅰ 教育理念の形成過程
た。講義録は毎月三回発行され、多くの人々によって哲学が学ばれた。
学生の一人であった河口慧海は、鎖国状態にあったネパールやチベットに入って仏教原
典を持ち帰ったことで知られる仏教学者で探検家であるが、哲学館が創立されたときは二
十二歳で、はじめは学資がないので館外員として講義録を読んでいた。そのうち苦学を決
43
心して上京し、館内員となった。しかし、実際の生活はそうとうに厳しく、 「茶漬沢庵の
�
- ▲TOP