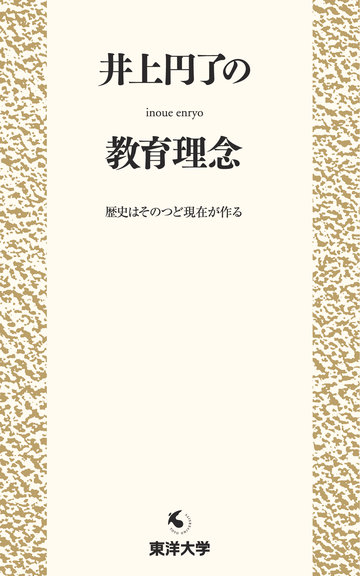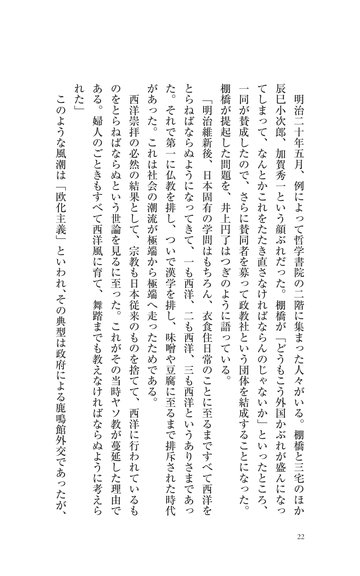井上円了の教育理念
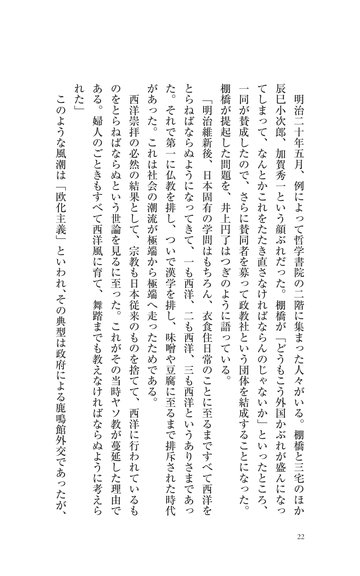
- ページ: 26
- 明治二十年五月、例によって哲学書院の二階に集まった人々がいる。棚橋と三宅のほか
辰巳小次郎、加賀秀一という顔ぶれだった。棚橋が「どうもこう外国かぶれが盛んになっ
てしまって、なんとかこれをたたき直さなければならんのじゃないか」といったところ、
一同が賛成したので、さらに賛同者を募って政教社という団体を結成することになった。
棚橋が提起した問題を、井上円了はつぎのように語っている。
「明治維新後、日本固有の学問はもちろん、衣食住日常のことに至るまですべて西洋を
とらねばならぬようになってきて、一も西洋、二も西洋、三も西洋というありさまであっ
た。それで第一に仏教を排し、ついで漢学を排し、味噌や豆腐に至るまで排斥された時代
があった。これは社会の潮流が極端から極端へ走ったためである。
西洋崇拝の必然の結果として、宗教も日本従来のものを捨てて、西洋に行われているも
のをとらねばならぬという世論を見るに至った。これがその当時ヤソ教が蔓延した理由で れた」
ある。婦人のごときもすべて西洋風に育て、舞踏までも教えなければならぬように考えら
このような風潮は「欧化主義」といわれ、 その典型は政府による鹿鳴館外交であったが、
22
�
- ▲TOP