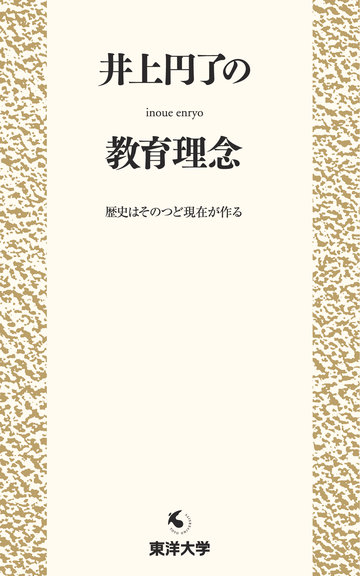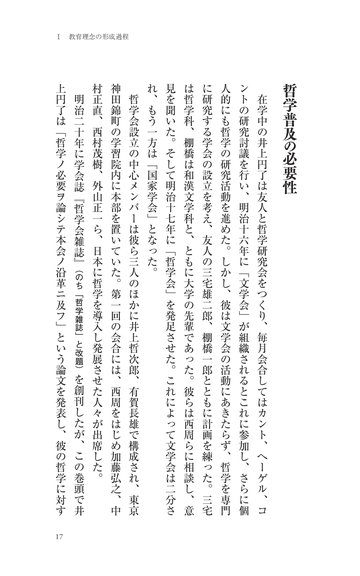井上円了の教育理念
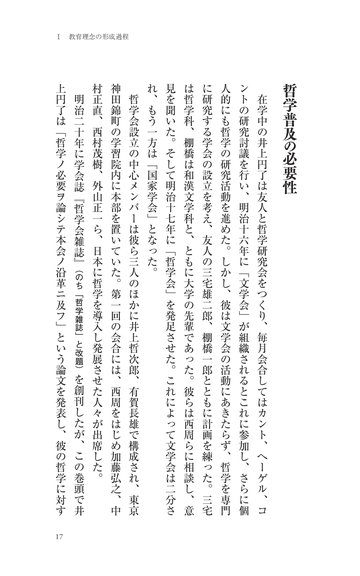
- ページ: 21
- 哲学普及の必要性
在学中の井上円了は友人と哲学研究会をつくり、毎月会合してはカント、へーゲル、コ
ントの研究討議を行い、明治十六年に「文学会」が組織されるとこれに参加し、さらに個
人的にも哲学の研究活動を進めた。しかし、彼は文学会の活動にあきたらず、哲学を専門
に研究する学会の設立を考え、友人の三宅雄二郎、棚橋一郎とともに計画を練った。三宅
は哲学科、棚橋は和漢文学科と、ともに大学の先輩であった。彼らは西周らに相談し、意 れ、もう一方は「国家学会」となった。
Ⅰ 教育理念の形成過程
見を聞いた。そして明治十七年に「哲学会」を発足させた。これによって文学会は二分さ
哲学会設立の中心メンバーは彼ら三人のほかに井上哲次郎、有賀長雄で構成され、東京
神田錦町の学習院内に本部を置いていた。第一回の会合には、西周をはじめ加藤弘之、中
村正直、西村茂樹、外山正一ら、日本に哲学を導入し発展させた人々が出席した。
(のち「哲学雑誌」と改題)を創刊したが、この巻頭で井 明治二十年に学会誌『哲学会雑誌』
17
上円了は「哲学ノ必要ヲ論シテ本会ノ沿革ニ及フ」という論文を発表し、彼の哲学に対す
�
- ▲TOP