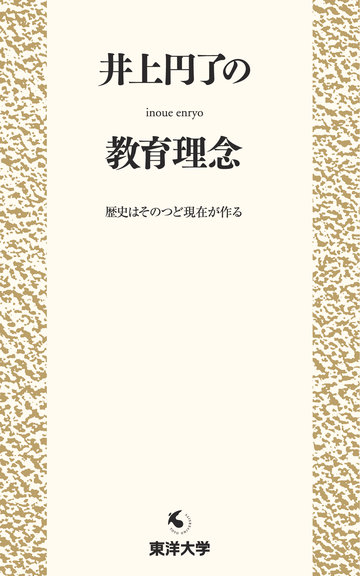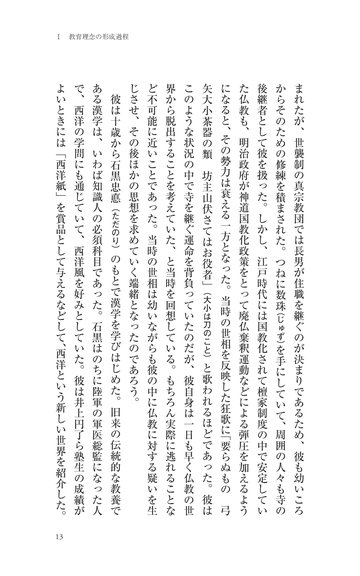井上円了の教育理念
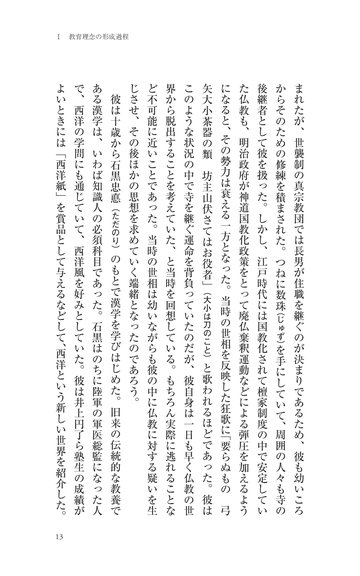
- ページ: 17
- まれたが、世襲制の真宗教団では長男が住職を継ぐのが決まりであるため、彼も幼いころ
(じゅず) からそのための修練を積まされた。つねに数珠 を 手 に し て い て、 周囲の人々も寺の
後継者として彼を扱った。しかし、江戸時代には国教化されて檀家制度の中で安定してい
た仏教も、明治政府が神道国教化政策をとって廃仏棄釈運動などによる弾圧を加えるよう
になると、 その勢力は衰える一方となった。当時の世相を反映した狂歌に 「要らぬもの 弓
(大小は刀のこと)と歌われるほどであった。彼は 矢大小茶器の類 坊主山伏さてはお役者」
このような状況の中で寺を継ぐ運命を背負っていたのだが、彼自身は一日も早く仏教の世
界から脱出することを考えていた、と当時を回想している。もちろん実際に逃れることな
ど不可能に近いことであった。当時の世相は幼いながらも彼の中に仏教に対する疑いを生
Ⅰ 教育理念の形成過程
じさせ、その後ほかの思想を求めていく端緒となったのであろう。
彼は十歳から石黒忠悳(ただのり)のもとで漢学を学びはじめた。旧来の伝統的な教養で
ある漢学は、いわば知識人の必須科目であった。石黒はのちに陸軍の軍医総監になった人
で、西洋の学問にも通じていて、西洋風を好みとしていた。彼は井上円了ら塾生の成績が
13
よいときには「西洋紙」を賞品として与えるなどして、 西洋という新しい世界を紹介した。
�
- ▲TOP