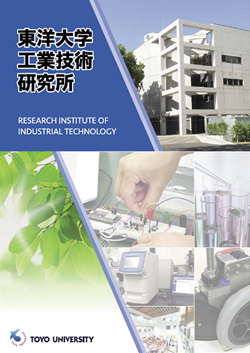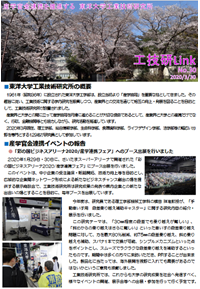Research 工業技術研究所
About
産業界との技術交流事業の窓口となり、
相互の発展をはかります。

概要
- はじめに
-
東洋大学は「哲学館」として1887年(明治20年)に設立されました。この時代の日本は、文明開化の真最中でありましたので、創設者 井上円了は建学の基本姿勢として、次のことを定めました。
- 真の文明開化をするためには、あらゆる学問の基礎に哲学をおかねばならないこと。
- 学を志す者は如何なる者でも。教育を受けることができるようにすること。
このように東洋大学は、創立以来、常に民衆の中に「開かれた大学」であることを願ってきました。
1961年(昭和36年)、このような流れの中で工学部が創設され、設立の趣旨も開かれた大学として「産学協同」を重要な柱としています。
この趣旨に従い、工学部創設と同時に工業技術研究会が設置され、産学協同事業の窓口として業務を開始しました。1975年(昭和50年)にはこの会を発展させて現在の「工業技術研究所」が設立されました。
設立時以来、研究所の構成メンバーの大部分は工学部の教員でしたが、1997年(平成9年)に生命科学部が創設されたことに伴い同学部の生命科学科の教員をメンバーとして迎え入れ、2002年(平成14年)7月には学内の研究組織の改革によりさらに法学部や社会学部の教員をメンバーに迎え入れ、研究所の研究分野は大きく広がりました。
当研究所は、工業技術に関する学内研究を振興しつつ、学外との交流を通じて相互の向上発展をはかることを目的としています。この目的にそって、産業界と大学との間に立って産学協同を円滑に進めることが大切な使命であると考えています。
当ホームページは、当研究所の活動内容と学内研究員の具体的な研究活動の内容を紹介しております。研究員との共同研究、委託研究・実験・試験、技術相談など大学と連携した活動をお考えの企業の皆様の手引きとしてご活用下されば幸いです。
- 概要
-
- 産業界セミナー
- 技術相談
- 受託研究
- 講演会の実施、冊子「講演会予稿集」の発行
- 懇談会・技術懇話会
- 共同研究
- 機関誌「工業技術」の発行
- 小冊子「東洋大学工業技術研究所紹介」、PR紙「工技研Link」の発行
- 産学連携プロジェクト研究の実施
- その他
このように工業技術研究所は、常に産学協同事業の窓口として業務を実施しています。
- 研究所のあゆみ
-
1961年 4月1日 東洋大学工学部(機械工学科、電気工学科、応用化学科)創設 1962年 4月1日 土木工学科、建築学科 新設 10月 工業技術研究所の前身「工業技術研究会」が発足 1975年 10月1日 東洋大学附置研究所として「工業技術研究所」を開設 応用化学科 赤星亮一教授 初代所長に就任 1976年 4月1日 工学部3号館において業務開始 情報工学科 新設 7月 第1回工業技術研究所所員会議を開催 11月 第1回工業技術研究所講演会、研究発表会を開催 工業技術研究所基礎研究費が交付され研究活動を開始 1979年 4月1日 工業技術研究所規程改正 7月 機関誌「工業技術」第1号を発刊 1980年 4月1日 第1回工業技術研究所プロジェクト研究を実施 1981年 4月1日 機械工学科 上原邦雄教授 第2代所長に就任 6月 「工技研ニュース」第1号を発行 11月 工学部創立20周年記念行事を挙行 1985年 4月1日 土木工学科 米倉亮三教授 第3代所長に就任 1987年 5月1日 工業技術研究所の将来計画を立案 10月 東洋大学創立100周年記念行事を挙行 1988年 4月1日 工業技術研究所内規改正 1989年 4月1日 建築学科 太田邦夫教授 第4代所長に就任 1990年 11月1日 工業技術研究所創立15周年記念パーティ、記念の技術フォーラムを開催 1991年 8月1日 工学部4号館新築に伴い3号館から4号館4階に移転 11月 工学部創立30周年記念行事を挙行 1992年 4月1日 電気工学科を電気電子工学科に名称変更 1993年 4月1日 土木工学科 後藤圭司教授 第5代所長に就任 1994年 4月1日 工業技術研究所規程・細則改正 1995年 4月1日 土木工学科を環境建設学科に名称変更 1997年 4月1日 板倉キャンパスに生命科学部を創設 機械工学科 清澤文彌太教授 第6代所長に就任 2000年 4月1日 教養課程廃止 2001年 4月1日 情報工学科 米山正秀教授 第7代所長に就任 コンピュテーショナル情報工学科 新設 2002年 7月1日 学術研究推進センター発足 学術研究推進センター及び研究所規程施行 工業技術研究所細則改正 規程廃止 2003年 4月1日 電気電子工学科 矢野昌雄教授 第8代所長に就任 10月 情報工学科 佐藤章教授 第9代所長に就任 2004年 4月1日 環境建設学科 坂本信義教授 第10代所長に就任 学術研究推進センター及び研究所規程改正 工業技術研究所細則改正 10月 「工技研Link」第1号を発行 2005年 4月1日 機能ロボティクス学科 新設 電気電子工学科を電子情報工学科に名称変更 コンピュテーショナル情報工学科をコンピュテーショナル工学科に名称変更 2008年 4月1日 電子情報工学科 石曽根孝之教授 第11代所長に就任 2009年 4月1日 川越キャンパスに総合情報学部 創設 工学部を再編し理工学部を設置 生体医工学科 新設 産学協同教育センター 発足 工業技術研究所細則改正 2011年 7月1日 工業技術研究所細則改正 10月1日 川越キャンパス開設50周年記念式典を挙行 2012年 4月1日 機械工学科 松元明弘教授 第12代所長に就任 7月1日 工業技術研究所賛助会員費の納入に係る取り扱い要領を制定 7月25日 退職された歴代会長・所長(計12名)に対し「名誉研究員」の称号を授与 2016年 4月1日 生命科学科 川口英夫教授 第13代所長に就任 2020年 4月1日 応用化学科 勝亦徹教授 第14代所長に就任 2022年 9月7日 工業技術研究所発足60周年記念行事 講演会開催 2023年 10月1日 工業技術研究所 細則改定 2024年 4月1日 建築学科 香取慶一教授 第15代所長に就任 工業技術研究所 細則改正
活動内容
工業技術研究所の主な活動内容は、「大学から産業界への協力」、「産業界から大学への協力」、そしてそれが融合して生まれる「産業連携」です。
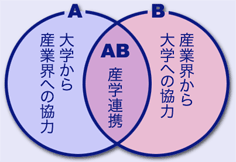
- 大学から産業界への協力
-
企業内技術者の教育
出張講座
出張講座は企業内技術者に対して、教育を目的とした講座を行う制度で、内容は一般論、基礎論、応用、先端技術から将来展望に至るまで多岐にわたります。講師は原則として研究所研究員があたり、企業に出張して行うことを原則としています。講座は90分を1単位とし、1~数単位で構成できます。
受講料は下の表のとおりですが、賛助会員は年間4単位まで無料とします。
単位 賛助会員 一般 1 30,000円 40,000円 技術相談
技術相談は産業界に対する工業技術研究所の顧問活動で、各専門分野を担当する研究員によって行われます。相談料は原則無料とします。技術相談の内容については秘密を厳守します。
受託研究
学外からの依頼を受けて大学で実施する研究が受託研究です。実施に当たっては研究課題ごとに研究目的・研究内容・研究担当者・研究期間・研究費・研究成果の公表・知的所有権の取り扱い等を協議し契約書を取り交わします。受託研究費は協議により定めます。研究費には総額に応じて細則第23条表2の率を乗じた金額を受託事業運営費に繰り入れます。学問的に意義のある成果が得られた場合には、両者で協議の上、研究終了後早い時期に学会等に発表することを原則とします。
学術講演会、特別講演会の開催
研究員の研究成果発表のための学術講演会を年に数回開催します。また、年に2回開かれる研究員総会にあわせて、特別講演会を開催し、いろいろな分野で活躍されている大先輩、第一線の研究者、技術者の方々をお招きして示唆に富むお話を伺っています。何れも、聴講は無料です。
- 産業界から大学への協力
-
学生実習の受入れ
東洋大学工学部の創設趣旨の大きな柱に「産学協同」があります。この中の重要な部分に学生の学外での実習が含まれています。学外実習は教学上の行事であって、研究所が直接に関与することではありませんが、賛助会員及び一般企業と大学の教学部門との間に立って、連絡、調整役をつとめています。内容などのお問い合わせは、研究所事務室または理工学部、総合情報学部の各学科教務室までお願いします。
賛助会員
工業技術研究所を通じて、大学と産業界とが教育の面と研究の面において協力し、その活動を促進するとともに、産業界における技術水準の向上を図り、ひいては国民生活の向上に貢献する趣旨に賛同いただける賛助会員を随時募集しています。年会費は下記の通りです。
年会費 賛助会員 120,000円 賛助会員には、以下のような特典が用意されています。
- 中核人材育成講座:年間2講座まで無料
- 出張講座:年間4単位まで無料
- 研究員と共同で行う産学連携プロジェクトへの応募
- 川越図書館の利用
- 機関誌「工業技術」等の送付
- 講演会、研究会等の案内
- その他、運営委員会が必要と認めた事項
- 産学連携
-
懇談会・技術懇話会
賛助会員及び一般企業、学内研究員の間の連絡連携を深め、親睦を図る目的で年に数回、懇談会、技術懇話会を開催しています。
共同研究
共同研究は新しいアイデアや基礎研究の成果に基づいて、工業技術研究所と学外の企業や研究所とが研究費を分担して共同で開発研究を行う制度であります。研究課題ごとに研究内容・研究担当者・研究期間・研究費・知的所有権の取り扱いなどを協議し契約書を作成します。学問的に意義ある成果が得られた場合には、両者協議の上で研究終了後早い時期に学会等に発表することを原則とします。
機関誌「工業技術」、「東洋大学工業技術研究所紹介」の発行
工業技術研究所の機関誌として「工業技術」を年に1回発行しています。内容は研究員による研究の成果報告、専門分野の総説、講演会での内容の要約、賛助会員会社紹介などが盛り込まれています。当研究所研究員の具体的な研究活動の内容を紹介した冊子「東洋大学工業技術研究所紹介」は必要に応じて発行しています。
(賛助会員との)産学連携プロジェクト研究
産学連携プロジェクト研究は工業技術研究所が賛助会員企業に対して、研究員と一緒になって開発研究するテーマを募集して実施する制度で、年間2~3件のプロジェクトが実施されています。研究終了後、機関誌「工業技術」に研究成果を発表します。賛助会員から頂いた会費を原資としています。
プロジェクト研究
プロジェクト研究は工業技術研究所が研究員に対して研究テーマの募集をして研究を実施する制度で、年間2~3件のプロジェクトが実施されています。研究終了後、早い時期に学会等に発表することを原則としていますが、機関誌「工業技術」に研究成果を発表します。賛助会員から頂いた会費を原資としています。
研究員紹介
賛助会員紹介
- 企業一覧(2023年10月1日現在)
-
初雁興業株式会社 埼玉県川越市 日油技研工業株式会社 埼玉県川越市 株式会社松永建設 埼玉県さいたま市 株式会社日東 埼玉県坂戸市 株式会社東洋クオリティワン 埼玉県川越市 アキム株式会社 埼玉県東松山市 株式会社スタック 埼玉県狭山市 株式会社ソマールゴム 埼玉県狭山市 サンリット工営株式会社 東京都墨田区 武州ガス株式会社 埼玉県川越市 電子磁気工業株式会社 東京都北区 株式会社マイクロ・テクニカ 東京都豊島区 通信興業株式会社 埼玉県川越市 株式会社谷野製作所 埼玉県日高市 大起理化工業株式会社 埼玉県鴻巣市 入間ガス株式会社 埼玉県入間市 伊田テクノス株式会社 埼玉県東松山市 株式会社日立プラントサービス 東京都豊島区 有限会社佐藤酒造店 埼玉県入間郡越生町 株式会社興電舎 埼玉県北本市 株式会社CRYO SHIP 埼玉県さいたま市 セントラル科学株式会社 東京都文京区 株式会社ショーナン 神奈川県藤沢市
金融機関との連携
- 連携先金融機関一覧
-
埼玉県川越市に位置する工業技術研究所は、地元各種金融機関と産学連携にかかる協定を結んでいます。
多くの連携機会の提供と企業の紹介を受けながら、地元中小企業および地域社会の活性化に寄与すべく取り組んでおります。
連携先金融機関名一覧 (締結日順)
(2009年10月1日現在)
金融機関名 締結日 協定内容 武蔵野銀行 平成17年4月1日 企業等からの技術等の相談対応
企業等からの共同研究等の推進
大学発ベンチャーの推進・支援
その他産学連携推進活動に寄与する事項の推進飯能信用金庫 平成18年7月19日 企業等からの技術等の相談対応
企業等からの共同研究等の推進
大学発ベンチャーの推進・支援
その他産学連携推進活動に寄与する事項の推進川口信用金庫 平成18年10月10日 民間企業等との共同研究等
技術相談
科学技術情報に関する講演会、セミナー、見学会等
大学発ベンチャー等新事業創出のための技術移転等の推進埼玉りそな銀行 平成18年12月1日 産学連携推進活動に係る事項についての相互協力 埼玉縣信用金庫 平成20年3月7日 民間企業等との共同研究等
技術相談
科学技術情報に関する講演会、セミナー、見学会等
大学発ベンチャー等新事業創出のための技術移転
その他目標達成のための必要項目日本政策金融公庫 平成21年10月1日 研究成果等のシーズと地域中小企業の技術ニーズとのマッチングのコーディネート
技術相談
地域中小企業の技術ニーズの情報提供
その他産学連携の協力推進にかかる必要事項
各種お申し込み
工業技術研究所では工学に関する各種相談を受け付けております。以下の申込書から適当な申込書をダウンロードしていただき、ご記入の上、工業技術研究所まで郵送またはe-mail等でお送りください。
「手続の方法がわからない」、「希望する申込書がみつからない」など、ご不明な点がございましたらご遠慮なくお電話か電子メールで工業技術研究所までご相談ください。なお、費用につきましては「活動内容」をご覧下さい。
工業技術研究所の連絡先(書類発送先)は以下の通りです。
〒350-8585 埼玉県川越市鯨井2100
東洋大学 工業技術研究所
- TEL:049-239-1322
- e-mail:kougiken(アット)toyo.jp
※メール送付の際は「(アット)」を@に置き換えてください。
工業技術研究所賛助会員へ入会を希望される方へ
技術的なご相談をご希望の方へ
企業内での教育を目的とした講義をご希望の方へ
刊行物バックナンバー
- 工業技術
-
「工業技術」は、産学官連携研究の推進と情報公開による開かれた大学の実現を目的として東洋大学工業技術研究所が発行する研究情報誌です。
- 工技研 Link
-
工技研Link は、東洋大学における産官学連携の窓口となっている東洋大学工業技術研究所が発行しているコミュニケーションペーパーです。当研究所が主催するイベントや出展するイベントに関する情報を掲載することで、研究所所員、賛助会員、行政、市民とがLinkすることを推進します。イベント会場等で配布します。
- 2019年以前のバックナンバーはこちら(工技研 Link)
-
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004