村上龍の小説『最後の家族』をテーマに、「家族」について考えてみます。
小説に登場する内田家は一見ごく普通の核家族ですが、父親は会社が倒産し失業、息子は1年半以上引きこもっています。家族は崩壊しそうになりつつもそれぞれの道を見つけた結果、家族全員が別々の場所に暮らすことになります。1年後に再会した時、父親は人に「おれの、家族なんだ」と紹介して終わります。
彼らを家族として枠付けているのは何でしょう。この小説で残るのは「お互いを思いやる感情」です。一定の時間と環境と思いを共有して、その後ばらばらになってもやはり家族でいられる。それは“同窓会”家族ともいえるかもしれません。また、タイトルにある“最後の”は、典型的な戦後日本の核家族というカタチを失い、「新しい」家族の姿を表現しているのではないでしょうか。
この小説が発表されたのは2001年で、当時は41万世帯が社会的引きこもりを抱えていました。また失業率は高く、社会や家族の歪みが噴き出ていた時代でした。このような当時の社会との関係や当時の意識のあり方なども含めて作品を読むことは、とても大切です。それによって、初めて文学作品のアクチュアリティ(現実性)や現代性が見えてくるのです。
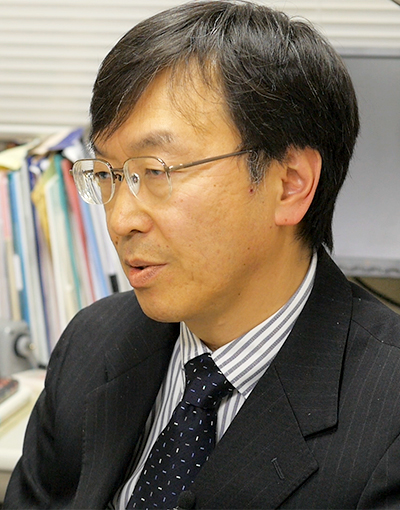
石田 仁志教授文学部 国際文化コミュニケーション学科
- 専門:日本近現代文学
- ※掲載内容は、取材当時のものです



