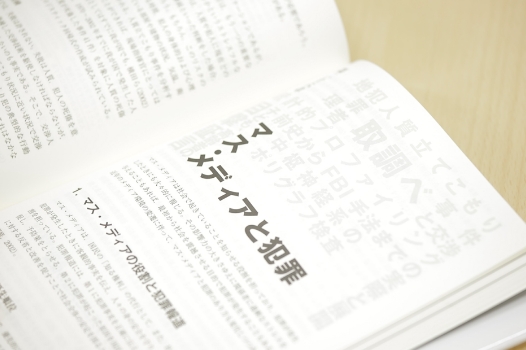Faculty of Sociology 社会学部 白山キャンパス
社会というフィールドに、
「理論」と「実証」の光を
アイデンティティ、ジェンダーやセクシュアリティ、家族の在り方などの身近なテーマから、公害や地球温暖化、少子高齢化、異文化理解といった世界中の人々が関連する壮大な問題まで。社会学は時代に即した幅広いテーマに向き合います。
「理論」と「実証」を軸とした研究方針の下、最新の研究成果や情報処理などの知識を蓄え、現地を訪ねて観察するフィールドワークやデータから規則性を導く統計分析などの手法に応用実践します。自らの手でフィールドから導き出した結果から、私たち人間社会が抱える問題の核心に迫ります。
Philosophy
社会学部で
「哲学すること」を学ぶ
東洋大学では、先入観や偏見に捉われず物事の本質に迫り、自分の問題として考え、他者のために考える姿勢を身に着けることを大切にしています。歩みを止めず、ともに考え続ける本学の学生にクローズアップし、「『哲学すること』とはどういうことなのか」を紐解きます。
About
社会の本質は「フィールド」にある
理論と実証で現代社会の諸問題に挑む
人間や社会の本質は、書籍やインターネットの情報からではなく、現象が起こっている現場、すなわち「フィールド」の観察を通して導き出すものです。社会学部が重きを置く社会調査関連科目では、学理を応用し、フィールドに深く踏み込んで学ぶ教育を展開しています。社会学の知を生かし、社会の諸問題に多角的に挑む力を養います。
教育の目的・ポリシー
- 教育研究上の目的
-
- 1.人材の養成に関する目的
-
社会学部は、古今東西の知の摂取と融合ならびに理論と実証に基づく実践主義を背景に、現代社会の諸問題に鋭く切り込む視座を涵養する人材育成を目標としている。
人権と社会正義の価値を重視し、現代社会をグローバルな視点から見据え、身近に存在する課題を発見し実証的に研究する力量を養うことを目的とする。
人間社会の持続可能性を支え、日本国内だけでなく、世界に広がるさまざまな現代社会の諸問題に関心を寄せ、さらには解決をめざすグローバル市民の育成をめざしている。
- 2.学生に修得させるべき能力等の教育目標
-
社会学部の教育理念は「理論、実証、実践の結合」である。この理念の実現のために、以下のような知識や能力の修得を目標としている。
- 演習科目を通して、基本的なコミュニケーション能力と主体的な学習能力を修得する。
- 多様な学部専門科目を通して、基礎的な社会学の理論や専門分野における研究成果についての知識を修得する。
- 「社会調査および実習」などの社会調査関連科目を通して、理論を質的・量的に検証しながら実証的に研究を行うコンピテンシーを修得する。
- 4年間の学部教育を通して、社会学の知識と技能を、社会貢献や、現代社会における諸問題の解決へと結びつける実践力を修得する。
- ディプロマ・ポリシー
-
社会学部では、以下に示す学修成果を上げることを、卒業の認定及び学位授与の条件としている。
- 諸学の基盤となる科目を幅広く履修し、柔軟な思考能力を養うこと。
- 社会調査に関する知識・技能を含めた社会学の基本的な知識を修得すること。
- 現代社会の様々な事象に関して、自ら考えながら学び、専門的な知識と実践的な応用能力を身につけること。